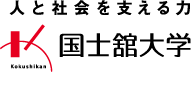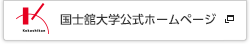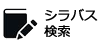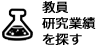本企画では、文学部の専任教員が「どんな専門なのか」「何が勉強できるのか」といった内容を中心に、受験生の皆さんへのメッセージを含めたショートエッセイを執筆しました。どうぞお楽しみください。
地理学の魅力を高校教員として伝える
桐越 仁美(きりこし ひとみ)講師(専門分野:地理学、アフリカ地域研究)
2023年3月に卒業した白石黎さんは、現在、東京都立の高等学校にて地理歴史科教員として勤務しています。地理を担当しており、2022年から始まった必修科目の「地理総合」と選択科目の「地理探究」を教えています。地理を専門として学んでいた教員は校内で白石さんのみであることから、校内の地理に関する業務において中心的な役割を担っています。
国士舘大学在籍時は、教員免許の取得と教員採用試験合格を目指し、大学の授業に関する勉強に加えて、採用試験に向けての勉強に励んでいました。また、地理に関わる授業を積極的に受講し、知識を身につける努力を欠かさなかったそうです。
現在は、在学時に身につけた地理や地図についての基礎的な知識や考え方を活かした授業をおこなっています。また、地理学野外実習や卒論で蓄えた、物事を多角的・多面的にとらえて分析する力、そしてその結果を文章等で表現する力も、いろいろなシーンで活かされています。
 高校教員として活躍する白石さん
高校教員として活躍する白石さん 地理学野外実習Cで調査報告をおこなうゼミ生(右から4番目が白石さん)
地理学野外実習Cで調査報告をおこなうゼミ生(右から4番目が白石さん)
<2023年 8月 1日(火)掲載>
専門を生かしたキャリアデザイン
長谷川 均(はせがわ ひとし)教授(専門分野:地形学)
「せっかく地理や環境を学んだのだから、専門を生かしたキャリアデザインを考えてほしいな」と言い続けています。ゼミ生を見ると、そういう道を選んだ人と、そうでない人は、3:7くらいでしょうか。
私が日本地理学会で企画専門委員をやっていた時、地理学の就職先を広げようという話になりました。それで作ったのが「地域調査士」と「GIS学術士」資格です。この時は、後に地理学会会長、理事長になる方、国土地理院長、ゼネコンの執行役員、中堅の官僚などの経験者など、地理出身で各方面で活躍している方々の強力なバックアップがありました。
全国の地理系学科の中でも、本学は地理を生かした分野に就職する人の割合が高いです。即戦力になるようなことを意識して教えているわけではありませんが、地理・環境コースにはリテラシーだけでなくコンピテンシーの高い学生が多い結果かもしれませんね。
 卒論生が調べたブナの森(山梨県松姫峠付近)
卒論生が調べたブナの森(山梨県松姫峠付近)
<2023年 8月 4日(火)掲載>
生物地理の研究を生かした様ざまな進路の学生がいます:国立公園のレンジャーも!
磯谷 達宏(いそがい たつひろ)教授(専門分野:植生地理学、生態学、緑地計画論)
地理・環境コースの卒業生は、流通や金融などの一般的な進路に進む人も多くいますが、コースの学びの特徴を生かした進路に進む人の数も、毎年かなりの数にのぼっています。
磯谷ゼミの卒業生は、生物についての地理を卒業論文で研究するので、そのような特性を生かした進路に進む学生を数多く輩出してきました。環境調査会社で好きな生物を調べる仕事に就いた人、アウトドア・アクティビティーの会社のインストラクターになった人、市役所の環境政策課の職員になった人、大学院に進んで研究の道に進んだ人などが、ゼミから巣立ってきました。
近年では、国家公務員試験に合格して環境省のレンジャーとして国立公園で活躍している卒業生もいます。4年生のときは卒業論文で、ブナ林についての興味深い発見のある研究を行っていました。地理・環境コースの「ニュースレター」にレンジャーの仕事の紹介文が掲載されていますので、よろしければご覧になってください。
NEWSLETTER No.81
 (1MB)
(1MB)

<2023年 8月 8日(火)掲載>
観光業界への就職~最終面接での決め手
内田 順文(うちだ よりふみ)教授(専門分野:地理学)
私の主要な研究テーマは地理的イメージですが、たとえば軽井沢のイメージやパリのイメージのように、観光地のイメージも研究対象としていることから、観光地理学の授業も担当しています。その関係から、ゼミでは観光(観光地理学)をテーマに卒論を書く学生が毎年数名おり、観光関連の業種に就職する学生もけっこういます。卒業後に研究室を訪ねてくれる学生もいたり、近所のJTBの窓口で元ゼミ生とばったり出合ったりして、その際にはいわゆるギョーカイの話をよく聞くのですが、そのとき複数の卒業生から聞いた話を紹介します。
旅行代理店は昔から人気の就職先で、最終面接試験で早慶やGMARCHといった大学の学生と合格者の椅子を争うことになるというのはよくあるようです。その際に地理学を学んだということが大きなアピールポイントになり、とくに卒論で扱った観光現象について語ったことが採用につながったのではないか、と言うのです。たしかに志望者の多くが経済学部や法学部の学生という中で、地理を学んだこと自体が独自のアピールの方法になるというのはありそうな話です。もちろん最終面接に到達しなければ、地理学を学んだ特性を発揮することもできないので、採用試験の一次二次はまあしっかりと勉強してもらう必要はありますが。
 ゼミ巡検は観光地へ行くことが多いです。ここは大阪梅田のお初天神
ゼミ巡検は観光地へ行くことが多いです。ここは大阪梅田のお初天神
<2023年 8月 23日(水)掲載>
地図好きな学生が輝く!鈴木貴子さんのキャリア
加藤 幸治(かとう こうじ)教授(専門分野:経済地理学)
地理・環境コース(当時は専攻)・2016年3月卒の鈴木貴子さんは、入学前から「地図が好き!」という地理・環境コースにありがち(! ?)な学生のうちの一人で、現在は(株)ゼンリンで活躍中です。
地理・環境コースには地図製作の専門家はいませんが、そうした技術等は理系大学や専門学校で学ぶべきもので、地理・環境コースでの学びは地理や環境を考えるにあたって必要な地図・分かりやすい地図(主題図)とは?といったことを考えることに通じています。コンピュータソフトを作成する上では、プログラミング技術以上にユーザー目線に立ったソフトやアルゴリズムの設計も重要で、それには文系的観点も必要なことに似ています。急がば回れ!といったところ。
鈴木さんも地理・環境専攻では経済地理学的視点から宿泊施設の立地を把握・考察するといったことを専門にしており、卒業論文の成果は『国士舘大学地理学報告』25にも掲載されています。
 お店にて
お店にて 鈴木さんが製作にかかわった商品
鈴木さんが製作にかかわった商品
<2023年 8月 26日(土)掲載>