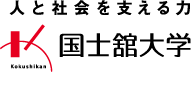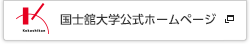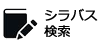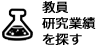本企画では、文学部の専任教員が「どんな専門なのか」「何が勉強できるのか」といった内容を中心に、受験生の皆さんへのメッセージを含めたショートエッセイを執筆しました。どうぞお楽しみください。更新は不定期です。
野外調査に基づく自然災害への備えを研究
佐々木 明彦(ささき あきひこ)准教授(専門分野:自然地理学、地形学)
地理・環境コースでは、卒業論文作成に向けた専門的な教育を受けるため3・4年次にゼミに所属します。佐々木ゼミでは、気象・気候や地形の調査方法と自然災害の発生メカニズムや防災・減災に関する課題を学びます。ゼミ生は自分自身でテーマを考え、野外調査にもとづいた研究に取り組んでいます。
動画でゼミ紹介:
地理・環境コースHP:http://bungakubu.kokushikan.ac.jp/chiri/index.html
 雲仙・普賢岳1991年噴火の火砕流堆積物の調査
雲仙・普賢岳1991年噴火の火砕流堆積物の調査 広島市の豪雨災害復旧現場の見学
広島市の豪雨災害復旧現場の見学
<2020年8月31日(月)掲載>
地理学の視点から考える経済とその空間的秩序
加藤 幸治(かとう こうじ)教授(専門分野:経済地理学)
企業や産業の立地や地理的な分布パターンとそれがもたらす影響について研究しています。主たる研究対象はサービス業で、近年は医療サービス(病院や診療所)の立地・配置と人口集積の関係について、「人口の都心回帰」「東京一極集中」のメカニズムにも注目して調べています。
地域振興などとも関連する話で、下記のような話とも関わります。
北海道新聞2020年2月22日掲載記事:https://www.hokkaido-np.co.jp/shichikosei/article2020022202
<2020年9月9日(水)掲載>
イメージのメカニズムから探る地理学と心理学と社会学の境界線
内田 順文(うちだ よりふみ)教授(専門分野:地理学)
専門は、「地理的イメージ」に関する研究です。例えば「銀座」や「金沢」や「スイス」という地名を聞いたときに、何か思い浮かぶもの、それが地理的イメージです。しかも、それはおそらく「錦糸町」や「川崎」や「バングラデシュ」について思ったときの内容とは違っているのではありませんか?実際、我々は日常生活の中で気付かぬ間に、ある場所に対してある決まったイメージを持つようになっているので、「吉野」は昔も今も桜の名所であり、「田園調布」と名がつけば土地の値段が上がり、演歌の主人公は「北」へ向かい、山陰の「小京都」に観光客が集まる、といった色々な現象が起こります。そのメカニズムを明らかにしようというのが主な研究テーマなわけで、いわば地理学と心理学と社会学との境界線に位置しているとでもいいましょうか。しかも近年、地理に関係するあらゆるイメージを扱うという点から、風景、文化、観光などにも興味を広げており、要するに自然・政治・経済・文化・歴史、その他「何でもあり」の研究で、その意味では、各方面への雑多な知識の集まりであった古代の地理学へ近づいているのかもしれません。
<2020年9月14日(月)掲載>
フィールドワークに基づき都市と交通の役割を研究
岡島 建(おかじま けん)教授(専門分野:都市と交通の歴史地理学)
岡島の専門は、都市と交通の歴史地理学で、近代都市発達における水上交通の役割を研究テーマとしています。ゼミでは、歴史地理学全般と交通地理学に関する研究方法と課題を教えます。ゼミ生は自分自身でテーマ(城下町や鉄道・バス関係が多い)を考え、資料収集や野外調査にもとづいた研究に取り組んでいます。
 佐倉城下町の構造について現地で説明
佐倉城下町の構造について現地で説明
<2020年9月16日(水)掲載>
アフリカと日本――地域の特性を知る
桐越 仁美(きりこし ひとみ)講師(専門分野:地理学、アフリカ地域研究)
専門はアフリカ地域研究・地誌で、西アフリカのニジェールとガーナをフィールドに、住民の自然資源利用や、交易を通じたネットワーク形成の実態を調査しています。ゼミ生は、日本の観光や農業などを切り口に、地域の特性や人びとの取り組みを明らかにする研究に取り組んでいます。
<2020年9月18日(金)掲載>
知的探究心を持って植生を研究
磯谷 達宏(いそがい たつひろ)教授(専門分野:植生地理学、生態学、緑地計画論)
私の専門は植生地理学で、「どこにどんな森林や草原があって、なぜそこにあるのか?」と問うのが基本姿勢です。このような研究は、公園などの緑地の管理にも役立っています。ゼミの学生には、植生の研究のほか、希望に応じて野生動物の生態地理などについても研究してもらっています。より詳しい研究紹介が次のサイトにありますので、ご参照ください。
研究活動に関するニュース:植生地理学の視点から地域の生態を理解する
 2年生の地理学野外実習にて(右端が磯谷です)
2年生の地理学野外実習にて(右端が磯谷です)
<2020年10月7日(水)掲載>