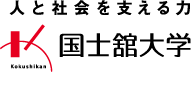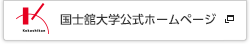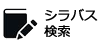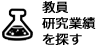本企画では、文学部の専任教員が「どんな専門なのか」「何が勉強できるのか」といった内容を中心に、受験生の皆さんへのメッセージを含めたショートエッセイを執筆しました。どうぞお楽しみください。更新は不定期です。
互いに学びあい、理解を深めあう
磯谷 達宏(いそがい たつひろ)教授(専門分野:植生地理学、生態学、緑地計画論)
私の専門は森林や草原などを対象とした植生地理学ですが、3・4年生が所属するゼミでは、生物の生態地理に関するテーマであれば、幅広いテーマの中から学生が学びたいテーマを選んでもらっています。そのためゼミは、教員の私を含めたゼミ生の皆で、さまざまな生きものの分布や生態についてお互いに学びあう場になっています。植生のほかシカやイノシシなどの哺乳類の研究がよく行われますが、鳥や魚、昆虫などについてのテーマ選択も自由です。とくに3年時の野外実習では、里山地域に行って皆で多種多様なな生きものを調べて報告しあい、地域の生態環境についての理解を深めていきます。私もこの実習を通して、さまざまな生きものについて学ばせてもらってきました。
研究活動に関するニュース:植生地理学の視点から地域の生態を理解する
 魚類を調べる学生に草原を調べる学生が合流したところ
魚類を調べる学生に草原を調べる学生が合流したところ
<2020年12月4日(金)掲載>
学生たちと過ごすパワフルな野外実習
佐々木 明彦(ささき あきひこ)准教授(専門分野:自然地理学、地形学)
私のゼミの人数は例年10~15人です。3年次の3泊4日の野外実習では、ゼミ生は自分たちで決めた4つほどのテーマに分かれて地形や気候などの野外調査を実施し、私はそれぞれのグループ間を行ったり来たりして指導します。たとえば今年の実習では、一日の最低気温を観測するために気象調査のグループと夜明け前に出かけ、ホテルに戻ると、朝食をとって私を待っている地形の調査のグループとすぐに出かけ……という具合です。なんだか一番忙しいのは実際に調査をしている学生ではなく、わたし? 今年の実習もヘトヘトになりました(笑)。
動画でゼミ紹介:
地理・環境コースHP:http://bungakubu.kokushikan.ac.jp/chiri/index.html
 地すべり地形の調査を行うゼミ生たちが、地すべり末端の構造を川の対岸から観ている様子
地すべり地形の調査を行うゼミ生たちが、地すべり末端の構造を川の対岸から観ている様子
<2020年12月8日(火)掲載>
土地の文化を知るのに重要な「食の現地調査」
内田 順文(うちだ よりふみ)教授(専門分野:地理学)
おそらく地理・環境コースに所属する学生の多くにとって、大学生活4年間の中で最大のイベントは3年次の「地理学野外実習C」ではないかと思います。例年私のゼミでも、私の専門である認知行動論地理に興味のある学生のほか、観光地理・文化地理・都市地理といった多様なテーマを指向する学生が各自のテーマで実習に取り組んでいますが、学生たちが終日現地調査に汗を流している4日間、実習Cに関する私の仕事はというと、実施直前までの学生のテーマ設定・調査目的・調査方法の指導やケアといった学術部門はほぼ終了しているので、実習中の最大の役目は、いかにして少ない経費の中で安価に実習地の名物料理や美味しい食事を手配するかになります。「食事」はその土地の文化や歴史を知るための重要な調査対象でもありますので。札幌巡検でのジンギスカン・寿司・ジンギスカンの食べ放題サンドイッチ形態の3日間、大阪巡検でのキタとミナミのバイキング食べ比べ、那覇巡検での連日のステーキ三昧、どれも土地の名物をおなか一杯食べている学生の姿が思い出されます(ただ残念ながら、近年は経理上の融通が以前ほど利かなくなってしまい、これらは文字通り懐かしい思い出となってしまいました)。
 札幌での寿司三昧
札幌での寿司三昧 大阪の「551蓬莱」本店
大阪の「551蓬莱」本店
<2020年12月25日(金)掲載>
やる気のある学生で作る野外実習
加藤 幸治(かとう こうじ)教授(専門分野:経済地理学)
地理・環境コースでは野外実習が必修科目です。基本的に1年次向けの地理学野外実習A、2年次向けの地理学野外実習Bがそれぞれ1泊、3年次のゼミ単位による地理学野外実習Cでは3泊の泊まり込みで実習が行われます。また、あらたに地理学野外実習Dが選択科目としても今年(2020年度)から実施されるようになりました。日帰り2回の授業ですが、「やる気」ある履修生が参加する実習は教員・学生相互に充実した実習となりました。始まったばかりの授業なので、皆で・皆が「作る」授業といえるものです。「やる気」満々な人の参加を待ってます。
 2020年度地理学野外実習D(加藤コース) 品川区内で実施の一コマ
2020年度地理学野外実習D(加藤コース) 品川区内で実施の一コマ
<2021年1月15日(金)掲載>
学生とともに学ぶ新しいゼミ
桐越 仁美(きりこし ひとみ)講師(専門分野:地理学、アフリカ地域研究)
私は今年の4月に着任したばかりで、今年のゼミは3年生しか所属していません。まだ学生の人数は少ないですが、それぞれ観光や農業、交通、ものづくりなどの多彩なテーマに興味を持ち学んでいます。10月には3泊4日の野外実習に行き、学生がそれぞれに決めたテーマに応じて、商店街や駅前を対象に聞き取り調査などをおこないました。宿泊所では毎晩、面談の時間を設けて学生が収集したデータとにらめっこ。「こういう調査も必要?」「このデータをどう見る?」とディスカッションを深めるなかで、私も一緒に学ばせてもらいました。
 野外実習中の調査風景。レンタサイクルで街中を走り回り調査しました
野外実習中の調査風景。レンタサイクルで街中を走り回り調査しました
<2021年1月19日(火)掲載>
大学で鉄道や交通を学ぶなら国士舘へ
岡島 建(おかじま けん)教授(専門分野:都市と交通の歴史地理学)
地理が好き、地図が好きという学生には鉄道好きも多い。地理教員の中にもそういう人は少なくない。ところが、鉄道や交通の地理学を学べる大学はあまりない。本学はその稀少な一校であり、その講義を担当しているのは私である。大学で鉄道や交通の勉強がしたくて本学に来る学生も多い。卒論でも交通の調査・研究をやりたい人は岡島ゼミでもよいが、卒論は自然地理や都市地理にしたいと、他のゼミに進む学生も少なくない。また、鉄道会社に就職する学生も毎年数名おり、卒業後鉄道会社の社員となったOBが大学に来て 在学生と交流する場面もある。
 2016年地理学野外実習Cで、高松琴平電鉄車両工場を見学
2016年地理学野外実習Cで、高松琴平電鉄車両工場を見学
<2021年2月9日(火)掲載>