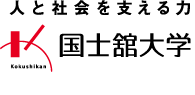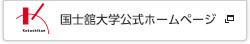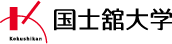東日本大震災以降、首都直下型地震が想定され、国民の多くが災害に対して不安を増幅させている現状を鑑み、全学を挙げて緊急時に即応できる防災リーダーを養成することが本学にとって喫緊の課題と考えています。防災・救急救助総合研究所は、各学部における防災教育力の向上を第一に考え、以下の防災教育を展開しています。
全学生へ向けた防災教育及び防災リーダーの育成

防災・救急救助総合研究所では、全学部の新入生を対象とした「防災総合基礎教育」を入学と同時に開講しています。また、1年生から受講できる、「防災リーダー養成論」(半期全15コマ)、「防災リーダー養成論実習」(大学への宿泊を含む3日間の集中講義)、「災害とドローン」(3日間集中講義)という、多彩な防災教育を行い、自助・共助・公助に関わる実践力を養っています。さらに、防災・救急救助総合研究所の教員が講師となり、民間資格「防災士」を大学内で取得できることで、多くの学生が学外資格を取得し、就職活動のみならず、各学部の専門性に多角的な視点を加え更に発展させることに寄与しています。
期待される成果
- 本学の学生となったその日から、自身の身を守ることができる知識を備える事ができる。
- 座学・演習を通じ系統立てて防災を学ぶことにより、共助の実践力を養う事ができる。
- 防災に関する学びや資格取得を通じ、学生の専門分野を更に発展させ、実践的な社会との関わり方や広く人々のために貢献する意思を形成できる。
災害ボランティア等の実践に基づく実学

災害発生時には被災地の復旧・復興をお手伝いする災害ボランティア活動に学生と一緒に取り組みます。災害現場では、ボランティアセンターの運営補助、被災者のニーズ調査、がれきの撤去、泥かき、衛生管理など多くの支援が求められます。近年、各地で自然災害が多発していますが、被災地の復旧・復興や被災者の生活再建に向けて、ますますボランティアの力が必要になってきています。私たちは被災地で即戦力として活躍できる人材を育て、全国で発生する災害の復旧・復興に貢献できる人材を数多く育てたいと考えています。被災者に寄り添い、災害に適切に対応できる人材を育成するためには、災害現場を体験することが欠かせないと考えています。
期待される成果
- 社会の構成員として、共助の精神に基づく積極的な活動意思(ボランティア精神)を形成する。
- 実際の災害現場に行って活動することで、教室で得られる知識だけでなく、実践的なスキルの修得や防災意識を向上させる。
- 「泥や瓦礫だけを見ずに、人を見る」をモットーに、世の為、人の為に尽くせる人材を育てる。
地域の教育機関や住民と連携した防災訓練

防災・救急救助総合研究所では、地域防災力の向上を目的に地域の様々な機関と連携しています。本研究所では地域の小中高等の教育機関や特別支援学校にも出向き、学校教職員が担う事が出来ない、専門的な防災教育を提供しています。また、本研究所が主体となって防災シンポジウムを毎年開催し、地域住民を中心に多くの方が聴講に来ています。令和5年3月には、災害情報学会と共催で第11回目となるシンポジウムを開催しました。さらにシンポジウムと同時に本学が中心となった防災訓練も開催し、地域住民や地元企業、日本赤十字社、警察、消防と連携した実践的な訓練の企画・運営も担っています。このような実践的な社会活動に本学の学生も携わることで、卒業後にどのような社会貢献が必要なのか見識を深める機会にもなっています。
期待される成果
- 住民・地元企業を含む地域防災力の向上
- 地域の教育機関との連携による小中高生の防災意識の向上
- 本学学生が卒業後の地域貢献を考える契機作り
ドローンを用いた研究及び学生への教育

ドローンは急速に進化し、防災分野だけでなく、様々な分野で有効活用され始めています。しかし、関連する法律やルールが複雑であり、国家資格を有する人材は乏しく、社会課題を解決するに至っていない現状があります。社会を支える人材育成を目標とする大学として、防災・救急救助総合研究所では他の教育機関に先駆け、ドローンに関する教育・研究活動を行っています。2023年から授業科目「災害とドローン」を開講し、全学部の学生が学部の垣根を超えて共に学びあっています。また、海、河川、雪山における人命救助を学ぶ授業や研究に協力し、多角的な視点を社会に提供しています。さらに、学生・卒業生・本学関係者には大学内でドローンの国家資格を取得できる体制を整え、既に多くの方が資格を取得することで、社会の負託に応えています。
期待される成果
- ドローンに関する専門知識と国家資格の取得
- 学部の垣根を超えた学びによる多角的な視点の涵養
- 先進的な技術を適切に扱うためのリテラシーや、社会課題を解決に導くプロセスの理解
スポーツ傷害の研究

スポーツ界では科学的サポートが進む一方で、毎年アスリートの命や健康を脅かす重大事故が発生しています。これらの事故は小さなミスの積み重ねが原因であることが多く、ミスへの意識と学びが重要です。防災・救急救助総合研究所では、スポーツや大型イベント事故の原因を学び、予防策を考えることで、安全意識を持った人材を育成し、スポーツや身体活動を通じてより良い社会の実現に貢献します。
期待される成果
- スポーツ事故・傷害の発生原因や要因の調査
- スポーツ環境の安全安心体制の理解および構築
- スポーツ事故・傷害発生や再発予防の理解と教育
国際協力・交流

防災・救急救助総合研究所は、救急医療に関する国際協力等を通じて諸外国の現地政府や医療従事者と協働し、課題解決に取り組んでいます。また、諸外国の大学等からの視察や研究員の受け入れを積極的に行い、研究者・実務者との交流や、学生・院生の国際協力への参画を促進するなど、大学のグローバル化を推進しています。
期待される成果
- 防災・救急・救助に関する国際協力による人材開発
- 諸外国の研究者・実務者との交流・共同研究
- 大学のグローバル化の推進
イベント救護活動や,一次救命処置講習(BLS)

東京マラソンをはじめ、各地で開催されている市民マラソン、トレイルマラソン、東京都少年サッカー、地域の祭り等のイベント救護を実施しています。
また、『いのちの教育』として学校教職員、学生、生徒、児童、企業・行政機関等の職員等を対象に、心肺蘇生やAEDの使用法、エピペン等の使用法の講習会を実施しています。
期待される成果
- 社会に出て即戦力となりえる「救命力」の人材の育成
- 実践力を蓄え、経験値の高い学生の輩出
- 大学の資材を活用し、地域貢献活性化を図る