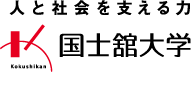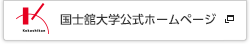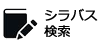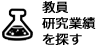本企画では、文学部の専任教員が「どんな専門なのか」「何が勉強できるのか」といった内容を中心に、受験生の皆さんへのメッセージを含めたショートエッセイを執筆しました。どうぞお楽しみください。
フィンランドにおける第二次世界大戦の記憶と表象
石野 裕子(いしの ゆうこ)准教授(専門分野:ヨーロッパ史)
現在、私はフィンランドにおいて第二次世界大戦の記憶がどのような形で人びとの間で共有されているのかを明らかにするために、歴史教科書における第二次世界大戦の叙述や博物館といった公共施設での説明などに注目して研究を進めています。
フィンランドは第二次世界大戦期にソ連と2度戦争をしました。1度目は冬に勃発したので「冬戦争」と呼ばれ、1939年11月から1940年3月まで続きました。2度目は冬戦争に続く戦争として「継続戦争」と呼ばれ、1941年6月から1944年9月まで続きました。
フィンランドはこの2度の戦争でソ連に敗北し、大きな代償を支払いました。その苦い記憶が現在まで人びとの間でどのように受け継がれているのかについて研究しているのですが、最近フィンランド内外で、ロシアのウクライナ侵攻と冬戦争とを重ね合わせて論じられている風潮に気がつきました。80年以上も前の戦争の「記憶」がフィンランドの人びとの間で蘇り、フィンランドのNATO加盟申請に賛同する世論の高まりにもつながりました。
このような現在起こっている動きにも注目しながら、第二次世界大戦の「記憶」について明らかにしていきたいです。
 ヘルシンキのヒエタニエミ墓地にある第二次世界大戦の記念碑
ヘルシンキのヒエタニエミ墓地にある第二次世界大戦の記念碑
<2022年8月2日(火)掲載>
ヒトの移動、カネの移動
久保田 裕次(くぼた ゆうじ)准教授(専門分野:日本近現代史)
私は日本近現代史を専門とし、中国に関する様々な問題が日本の政治や外交にどのような影響を与えていたのかを研究テーマとしています。特に注目しているのが、日本や欧米諸国の対中国投資(間接投資を指して借款といいます)であり、カネの移動の背後にある国際関係や国内政治を知ることに関心を持っています。
近年、ヒト・モノ・カネの移動は拡大の一途をたどっていました。多角的に日本や欧米の対中国投資を分析し、改めて日本の立ち位置を考えるために、私も海外で調査を行ってきました。イギリスやアメリカの国立公文書館に加え、対アジア投資に関するイギリスの代表的な銀行である香港上海銀行(HSBC)のアーカイブズなどで歴史資料の調査をするなど、ヒトである私も移動を繰り返しました。
グローバル化の象徴である対外投資を行っているのは感情を持ったヒトです。投資を知ることはヒトや社会を理解することであり、実際にヒトも資料を求めて移動しなければならないという思いを強くしています。
 ロンドン・シティの様子
ロンドン・シティの様子 HSBC香港本店前のライオン像
HSBC香港本店前のライオン像
<2022年9月6日(火)掲載>