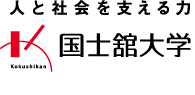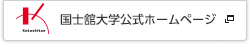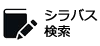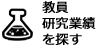国士舘大学政経学会は、大学という教育機関の中に設置された学術研究機関です。政治行政学科と経済学科の専任教員はもちろんのこと、非常勤講師や大学院生や学部生もこの研究機関の構成員になっています。学部生は、政経学部入学と同時に自動的にこの学会のメンバーになります。
「学会」と聞くと、学生の皆さんには無縁な遠い世界のように思われるかもしれません。しかし、皆さんはこのアカデミックな組織に所属する言わば「研究者」として扱われるのです。講義を受け、試験に合格し単位を取るという通常の大学での学びとは別に、ここでは自由な関心に基づく自主的な学びが可能です。
大学での学問が高校までの勉強とどう違うかについて、皆さんはすでに十分聞いているはずです。与えられた知識や解法を覚え、一定の時間内で正解へとたどり着くことが高校までの勉強の中心でした。それは点数評価され、偏差値として算出され、それをにらみながら皆さんは受験勉強をしてきたはずです。そのために、楽しいはずの学びが憂鬱になってしまったという思いを抱いている人も少なくないでしょう。大学にも覚えるべき知識はあります。解法、技法の習熟度を点数評価する仕組みはやはりあります。しかし、重要なのはそれが真の学びの土台であって終着点ではないということです。では、どうやって先へと歩を進めるのか。政経学会は、そのための様々な飛び石を用意しています。事業内容として、次ページにも紹介されていますが、それをもう少しかみ砕いて具体的に説明しましょう。
まず、学術誌『政経論叢』と『政経論集』の発行です。前者には政経学部の教員の最新の研究論文が発表されます。後者には大学院生の論文が掲載されます。教員や院生が互いにどのような研究をしているか、情報を交換し共有する場ですが、学部生の皆さんに自由な学問研究の多様な例を紹介する機会でもあります。200号近いバックナンバーを含めて、誰でも自由に閲覧することができますので、大いに参照し活用してください。
また、この学会では毎年ほぼ2回、外部の講師を招いて講演会を開催します。政治家や公務員、学識経験者、企業経営者、起業家、ジャーナリストなどにおいで頂き、普段の授業とは違った視点から、現場でのリアルな経験を踏まえて世界と日本の政治経済を語ってもらいます。平日の授業時間に実施されますので、授業の一環として組み込まれる場合もあります。会では、一方的に話を聞くだけでなく、学生の皆さんからの活発な質問や意見が期待されます。
学生自身の主体的な取り組みの場としては、「社会連携プロジェクト」と「学生優秀論文コンクール」があります。前者は、大学と実社会をつなぐものとして、専門ゼミナールの枠内で行われる社会貢献事業です。現在進められているのは、埼玉県八潮市と連携し、同市が直面する様々な課題に対して解決策を練り、発表するという取り組みです。今後も各地の自治体や企業とのこうした連携を企画し取り組んでいく予定です。
後者の「学生優秀論文コンクール」は、大学時代最大の課題と言える卒業論文の執筆を後押しするインセンティブです。「卒論」科目の単位付与とは別に、20名ほどの委員が審査をし、優れた論文に賞を授与し表彰する仕組みです。上でも触れたように、大学での学びは授業で与えられた知識や技能を単に覚えることではありません。それを基盤として自ら探求すべき課題を発見し、先行研究や資料を探して読み、場合によってはフィールドワークを行い、アカデミック・ルールに従いながら自分自身の頭で考えること、また他学生や教員との情報交換や議論をとおして問題を整理し、見通しや解決策を探る力をつけることこそが目標なのです。卒業論文の執筆はその達成度を問う最大の試金石です。将来どのような職業に就くにしても、このような真の学問経験は有用でしょう。学生の皆さんが積極的に挑戦してくれるよう、政経学部の教員一同が支援態勢を整えています。
大学教員は、教育者であると同時に、みな自分の専門領域を持つ研究者です。日々の授業や学務に追われて時間がないと嘆きながらも、コツコツと研究を進めています。学生の皆さんもまた、もはや「生徒」ではなく学問の主体であり、より良い社会のために実践的な知を切り開く者なのです。意欲をもって自分ならではの研究に挑戦してください。政経学会は、そのために全力で皆さんを応援しています。
プロフィール
 政経学会 学会長
政経学会 学会長生方 淳子 うぶかた・あつこ
- 1980年
- 青山学院大学文学部卒業
- 1983年
- 東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了(文学修士)
- 1984年
- フランス政府給費留学生としてパリに留学
- 1996年
- パリ第一大学(パンテオン=ソルボンヌ)博士課程修了(哲学博士)
国士舘大学専任講師
- 1997年
- 同助教授
- 2008年
- 同教授
- 1997年~2020年
- 青山学院大学、東京大学、立教大学、成城大学で非常勤講師を歴任
- 2005年~2007年
- お茶の水女子大学客員研究員
- 2015年~2016年
- フランス国立近代草稿研究所客員研究員
- 専門は哲学(現象学、存在論、科学認識論、倫理)
- 通算12年のフランス滞在とEU統合取材の経験から、ヨーロッパの政治、経済、社会の動きも注視
- 『交差する科学知』(共訳)、ユニテ、1987年
- 『サルトル21世紀の思想家』(共著)、思潮社、2007年
- 『死の人間学』(共著)、ミネルヴァ書房、2007年
- 『サルトル読本』(共著)、法政大学出版局、2015年
- 『戦場の哲学』、法政大学出版局、2020年