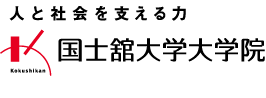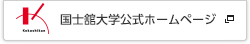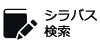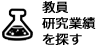概要
環境問題や教育を巡る深刻な問題に象徴されるように、近年の急激な社会状況の複雑化・情報化・国際化に伴い、人類文明と人間精神全般にかかわるような問題がさまざまな形で発生しています。現代の学問には、このような諸問題についての実態分析および対応策を構築することが切に求められています。人文科学においても、このような現代の状況を適切に把握し、それに積極的に対応することは時代の要請であり社会的使命でもあります。このような使命を担う人文科学の諸分野は、著しく発展、深化し専門性を強めていますが、一方では学際的研究が求められています。このような状況にある学問研究や社会の状況の分析に必要な視点、高度な情報処理能力を学部レベルの課程で修得することは困難であります。
本学では、これらに関する教育および研究、またこれらに的確に対応することができる専門的な知識・能力を身につけた人材を養成すべく、平成13年4月に人文科学専攻と教育学専攻からなる人文科学研究科修士課程を設置しました。
平成15年4月10日、これをさらに発展させ、歴史、文学・文化、地理・地域、教育を主軸とした教育・研究の場を設け、研究者として自立して研究活動を行い、またはその他の高度に専門的な業務に従事するのに必要な高度の研究能力およびその基礎となる豊かな学識を備えた人材を養成することを目的として人文科学研究科博士課程を開設致しました。
本研究科としては時代の状況を的確に把握し、教育・研究機関としての役割を果たすべく可能な限りの努力をしていきたいと考えております。
人文科学研究科の専攻・コースと研究分野
人文科学研究科修士課程には、人文科学諸分野における専門的な研究・教育を通じ、より高度の研究能力を開発・育成するとともに、新時代の要請に応えうる清新で高度な知識・能力を身につけた職業人を養成する目的で、人文科学専攻、教育学専攻の2専攻が開設されています。
| 研究科 | 専攻 | コース(学系) | 研究分野 |
|---|---|---|---|
| 人文科学研究科 | 人文科学専攻 | 考古・歴史学 | 日本史(考古学を含む) |
| 文学・文化論 | 日本文学/東洋文学 | ||
| 地理・地域論 | 人文地理/自然地理 | ||
| 教育学専攻 | 教育学 | ||
| 教職研究 | |||
研究分野と専修科目の選択
人文科学研究科の学生は、各専攻のうちに設けられたコースと研究分野のうちから、修士課程で専修しようとするl研究分野を1つ選び、後掲の各専攻開講科目一覧のうちから、研究指導を受けたい専修科目(演習)を1つ選択し、その担当教員および、その他の担当教員の研究指導を受けるものとする。
修士課程で授与される学位
人文科学研究科修士課程の各専攻に、原則として2年以上在学し、別に定める履修科目について所定の単位を修得し、かつ履修科目の試験の成績並びに修士論文の結果および最終試験(口頭試問)の成績の総合判定に合格した者に「修士(人文科学)」の学位を授与する。
専修科目の選択と研究指導
- 本研究科で学ぼうとする学生は、出願時に、人文科学研究専攻はコース・研究分野のうちから、教育学専攻は後掲開講科目一覧のうちから、入学後に専修する研究分野の1つを選択し、専修科目として登録します。
- 本研究科の学生は、出願時に登録しておいた専修科目(演習) を、年度はじめの履修登録期間中に履修登録し、その後は、この専修科目を担当する教員と、その他の科目担当教員を研究指導教員として研究指導を受け、研究計画を立てて研究活動を行い、修士論文を作成します。
- 専修科目として選択した科目(演習) は、原則として在学期間中にかならず8単位以上を履修し、単位を修得する必要があります。
- 毎学年、年度はじめに研究指導教員の指導を受け、履修科目を選択し、定められた期間中に履修登録を済ませます。履修する科目の選択は、人文科学専攻は登録した専修科目(演習) とともに、同じコース(学系) の開講科目を中心とし履修します。なお、教育学専攻専修科目からも選択履修できます。
教育学専攻では、登録専修科目(演習)ならびに専修科目以外の科目より選択履修します。人文科学専攻の専修科目以外の科目から、2科目まで選択履修できます。 - 学生は、指導教員の承認を得て、他研究科の講義科目4単位までを履修し。、修得した単位は専修科目以外の科目に含めることができます。
学位
修士(人文科学)の学位を修得するために、在学中に合計32単位以上修得する必要があります。かつ修士論文の審査および最終試験(口頭試問) に合格した者に「修士(人文科学)」の学位が授与されます。
修了単位
修得すべき単位数の基準は次表のとおりです。
人文科学専攻
| 年次 | 専修科目 | 専修科目以外の科目 |
|---|---|---|
| 第1年次 | 4単位 | 24単位以上 |
| 第2年次 | 4単位 | |
| 修了時 | 修得単位合計32単位以上 | |
教育学専攻
| 年次 | 専修科目 | 専修科目以外の科目 |
|---|---|---|
| 第1年次 | 4単位 | 24単位以上 |
| 第2年次 | 4単位 | |
| 修了時 | 修得単位合計32単位以上 | |
社会人の受入れ
- 人文科学研究科では、社会人のリカレント教育、または生涯学習の要請に応えるため、大学を卒業後満3年(大学院入学年度4月1日時点) 以上経過した者、または、満25歳(大学院入学年度4月1日時点) 以上の者については、「一般選考」とは別に、「社会人選考」を実施します。
- 「社会人選考」においては、「一般選考」で課される入学試験科目(専門科目と外国語科目、面接) のうちから、専門科目と外国語科目の2つが免除され、小論文と面接のみが行われます。
- 社会人選考の入学者は、一般選考入学者に比べ、学費において減免措置があります。
取得資格等
人文科学専攻における教員免許状の取得
- すでに、学部に開講されている教職課程を履修し、中学校社会科、中学校国語科、高等学校地理歴史科、高等学校国語科、高等学校書道科の1種免許状を取得している者は、人文科学専攻の課程を修了し、所定の科目から24単位を取得することで、それぞれの教科について専修免許状を取得できます。
- いまだ、教員免許状を取得していない者でも、人文科学研究科に在学期間中に、文学部に開講されている当該教職課程を合わせて履修することで、定められた単位を修得すれば、人文科学研究科の課程修了時に、中・高教員の専修免許状を取得することができます。
教育学専攻における教員免許状の取得
- すでに、学部に開講されている教職課程を履修し、幼稚園1種、小学校1種、中学校1種(社会、保健体育)高等学校1種(地理歴史、公民、保健体育) 免許状を取得している者は、教育学専攻の課程を修了し、専修免許取得希望教科に対応する科目から24単位以上修得することで、該当の校種・教科についての専修免許状を取得できます。
- いまだ、教員免許状を取得していない者でも、人文科学研究科に在学期間中に、文学部に開講されている当該教職課程を合わせて履修することで、教育職員免許法に定められた単位を修得すれば、人文科学研究科の課程修了時に、幼・小・中・高教員の教員免許状を取得することができます。
| 課程・専攻別区分 | 学部修了時に取得できる免許状 | 大学院研究科修了時に取得できる免許状 | |
|---|---|---|---|
| 人文科学専攻で取得できる免許状の種類 | 中学校1種 | 社会科 | 当該教科の専修免許状 |
| 国語科 | |||
| 高等学校1種 | 地理歴史科 | ||
| 国語科 | |||
| 書道科 | |||
| 教育学専攻で取得できる免許状の種類 | 幼稚園1種 | 当該教科の専修免許状 | |
| 小学校1種 | |||
| 中学校1種 | 社会科 | ||
| 保健体育科 | |||
| 高等学校1種 | 地理歴史科 | ||
| 公民科 | |||
| 保健体育科 | |||
研究科間単位互換制度
本学大学院では、10研究科を擁する総合大学としての特色を生かし、他研究科に配当された講義科目4単位までを所属する研究科の修了単位として認定する単位互換制度を設けています。
各研究科の得意分野を開放することにより、自己の研究テーマを幅広く検証することが可能となりました。さらに講義をとおして他研究科の教員および学生との交流の幅も広がるなどの利点もあり、毎年多数の学生が本制度を利用し、好評を得ています。
他大学院単位互換制度
人文科学研究科人文科学専攻は、他大学院との学術提携・交流を促進し、教育・研究の 充実を図ることを目的として単位互換制度を設けている。単位互換協定を締結した大学院間において、所属する大学院以外の協定校で授業科目を履修し、修得した単位をその所属する大学院の課程修了に必要な単位として認定する制度です。
史学系・地理学系・考古学系の3分野で、学術提携・交流を行っている。
単位互換を行っている分野および協定校
史学系分野の単位互換協定・協定校
- 青山学院大学大学院文学研究科史学専攻
- 中央大学大学院文学研究科国史学専攻・東洋史学専攻・西洋史学専攻
- 上智大学大学院文学研究科史学専攻
- 明治大学大学院文学研究科史学専攻
- 立教大学大学院文学研究科史学専攻
- 専修大学大学院文学研究科史学専攻
- 國學院大學大学院文学研究科日本史学専攻
- 駒澤大学大学院人文科学研究科歴史学専攻
- 東海大学大学院文学研究科史学専攻
- 東洋大学大学院文学研究科史学専攻
地理学系分野の単位互換協定・協定校
- 法政大学大学院人文科学研究科地理学専攻
- 駒澤大学大学院人文科学研究科地理学専攻
- 明治大学大学院文学研究科地理学専攻
- 専修大学大学院文学研究科地理学専攻
- 日本大学大学院理工学研究科地理学専攻
考古学分野の単位互換協定・協定校
- 昭和女子大学大学院生活機構研究科生活文化研究専攻
- 駒澤大学大学院人文科学研究科日本史学専攻
オンラインジャーナル
『国士舘人文科学論集』ISSN 2435-5690 第5号
| 題名 | 著者 | |
|---|---|---|
表紙&裏表紙 (86KB) (86KB) |
||
| 研究論文 | 近世日本における「無縁」「公界」「楽」 (620KB) (620KB) |
夏目琢史 |
| 研究論文 | メランヒトンのキケロー受容過程 (262KB) (262KB) |
菱刈晃夫 |
| 研究論文 | 在日中国人児童のウェルビーイングに関する研究――日本語能力に焦点を当てて―― (351MB) (351MB) |
楊慕姗・桜井美加・助川晃洋 |
| 研究論文 | 日本中世禅林における囲碁の「文雅化」――「四皓・橘中」伝説の変容をめぐって (702MB) (702MB) |
桑浩哲 |
| 研究論文 | 中古文学に見られる「心の鬼」― 散文作品を対象として ― (260MB) (260MB) |
鈴木健太朗 |
| 翻訳 | メランヒトン『神学要覧』(1559 年)―その 7 ―(Loci praecipui theologici.1559)翻訳 (238KB) (238KB) |
菱刈晃夫 |
| 翻訳 | 郭沫若「カルメラ娘」訳注(上) (306KB) (306KB) |
張琢月 |
| 教育実践報告 | 反転授業の予習段階における紙教材の活用可能性―アクティブ・ラーニングを促すために― (203KB) (203KB) |
助川晃洋 |
| 随筆 | 教育方法学の研究スタンス―教育社会学における学力格差論の基本構成と対比して― (157KB) (157KB) |
助川晃洋 |
| 研究紹介 | 大学院生研究紹介 (333KB) (333KB) |
大学院生 |
規約&奥付 (135KB) (135KB) |
『国士舘人文科学論集』ISSN 2435-5690 第4号
| 題名 | 著者 | |
|---|---|---|
表紙&裏表紙 (81KB) (81KB) |
||
| 研究論文 | メランヒトン「カテキズム」の特徴と展開 (417KB) (417KB) |
菱刈晃夫 |
| 研究論文 | 教材・教科書のデジタル化とその実践的意義 (263KB) (263KB) |
岡本翔・助川晃洋 |
| 研究論文 | 葬祭業のサービス産業化と葬儀会館の立地拡大 (1.26MB) (1.26MB) |
藤岡英之 |
| 研究論文 | 剣とペンと台湾引揚者―松川久仁男にみる戦後沖縄の再建― (3.35MB) (3.35MB) |
菅野敦志 |
| 研究論文 | 下野国分寺創建初期における三毳山麓窯跡群の位置づけ― 軒先瓦の比較分析から ― (2.85MB) (2.85MB) |
宇髙美友子 |
| 研究ノート | 教育改革における子どもの主体性の希求(続報)-OECDの「生徒エージェンシー」と「共同エージェンシー」の概念に関する小考- (257KB) (257KB) |
助川晃洋 |
| 翻訳 | メランヒトン『神学要覧』(1559 年)―その 6 ―(Loci praecipui theologici.1559)翻訳 (262KB) (262KB) |
菱刈晃夫 |
| 随筆 | 漢字と色彩 (215KB) (215KB) |
鷲野正明 |
| 随筆 | LOVOTが大学研究室に来た (201KB) (201KB) |
桜井美加・大浦邦彦・三上可菜子 |
| 研究紹介 | 大学院生研究紹介 (635KB) (635KB) |
大学院生 |
規約&奥付 (123KB) (123KB) |
『国士舘人文科学論集』ISSN 2435-5690 第3号
| 題名 | 著者 | |
|---|---|---|
表紙&裏表紙 (84KB) (84KB) |
||
| 研究論文 | 『講孟劄記』における吉田松陰と水戸学の関係 (330KB) (330KB) |
大場一央 |
| 研究ノート | メランヒトン『子どものカテキズム』の構造と特質 (250KB) (250KB) |
菱刈晃夫 |
| 研究ノート | 理科教授・学習プロセスマップの改良とその活用による理科授業デザイン支援 ― 教職実践演習における実践を通して ― (633KB) (633KB) |
小野瀬倫也 |
| 翻訳 | メランヒトン『道徳哲学概要』(その3) (354KB) (354KB) |
菱刈晃夫 |
| 教育実践報告 | 生徒参加実践としての学食改革― 宝仙Marchéの空間デザイン ― (187KB) (187KB) |
坂本徳雄 助川晃洋 |
| 随筆 | 高校教員として漢文を教えてみて (169KB) (169KB) |
中村隆志 |
| 自著紹介 | 『「大フィンランド」思想の誕生と変遷―叙事詩カレワラと知識人―』 (135KB) (135KB) |
石野裕子 |
| 自著紹介 | 伝統中国の文化に関する参考書:『中国ジェンダー史研究入門』ほか (162KB) (162KB) |
小川快之 |
| 自著紹介 | 『アンダーコロナの移民たち―日本社会の脆弱性があらわれた場所』 (144KB) (144KB) |
鈴木江理子 |
| 自著紹介 | B. グレトゥイゼン著『哲学的人間学』 (144KB) (144KB) |
菱刈晃夫 |
| 自著紹介 | 『朱熹『小学』研究』 (112KB) (112KB) |
松野敏之 |
| 研究紹介 | 大学院生研究紹介 (112KB) (112KB) |
大学院生 |
規約&奥付 (128KB) (128KB) |
『国士舘人文科学論集』ISSN 2435-5690 第2号
| 題名 | 著者 | |
|---|---|---|
表紙&裏表紙 (101KB) (101KB) |
||
| 研究論文 | 長崎市とその周辺における葬儀会館の立地と喪家の選択 (1729KB) (1729KB) |
藤岡英之 |
| 研究論文 | 曹丕『典論』研究 ― 武人としての矜持 (485KB) (485KB) |
永田諒乃・松野敏之 |
| 研究ノート | 教育改革における子どもの主体性の希求 ― OECDの「学習者のエージェンシー」概念に関するメモランダム (311KB) (311KB) |
助川晃洋 |
| 研究ノート | コロナから問う移民/外国人政策― 非常時に翻弄される「不自由な労働者」たち (358KB) (358KB) |
鈴木江理子 |
| 研究ノート | 明代沈周の「落花詩」について ― 一大風流韻事発端の十首 (398KB) (398KB) |
鷲野正明 |
| 研究ノート | 体育授業における発問の意義と課題に関する研究序説 (223KB) (223KB) |
吉岡正憲 |
| 翻訳 | 新発見 周恩来、郭沫若の往復書簡、呈文及び指示文 (2345KB) (2345KB) |
沈衛威 (訳)藤田梨那 |
| 翻訳 | メランヒトン『道徳哲学概要』(その2) (309KB) (309KB) |
菱刈晃夫 |
| 文献解題 | 富士晴英とゆかいな仲間たち『できちゃいました!フツーの学校』を読む― 宝仙学園中学・高等学校の教育実践から何を学ぶか (196KB) (196KB) |
助川晃洋 |
| 研究紹介 | 大学院生研究紹介 (406KB) (406KB) |
大学院生 |
規約&奥付 (126KB) (126KB) |
『国士舘人文科学論集』ISSN 2435-5690 創刊号
| 題名 | 著者 | |
|---|---|---|
表紙&裏表紙 (82.4KB) (82.4KB) |
||
巻頭言 (72.6KB) (72.6KB) |
菱刈晃夫 | |
| 研究論文 | 理科における「学びに向かう力」の背景と実践に向けた課題についての考察 (1.25MB) (1.25MB) |
石川正明・小野瀬倫也 |
| 研究論文 | 振動波エネルギーを転写した水(波動水)は精神的ストレス負荷からの回復に影響をあたえるか (354KB) (354KB) |
江川陽介 |
| 研究ノート | 郭沫若から三木清氏宛書簡 (1.18MB) (1.18MB) |
藤田梨那 |
| 研究ノート | 四角形の分類― 東アジアの4つの幾何学カリキュラム (366KB) (366KB) |
正田良 |
| 研究ノート | 子どもの投能力向上のポイントの整理と教材開発 (799KB) (799KB) |
宮崎琴子 |
| 翻訳 | メランヒトン『道徳哲学概要』(その1) (328KB) (328KB) |
菱刈晃夫 |
| 随筆 | マグパイ便り―2019年春夏イギリス・ヨークシャー滞在記 (1.13MB) (1.13MB) |
村上純一 |
| 研究紹介 | 大学院生研究紹介 (534KB) (534KB) |
大学院生 |
規約&奥付 (115KB) (115KB) |