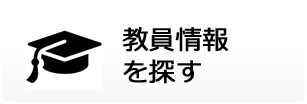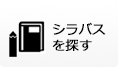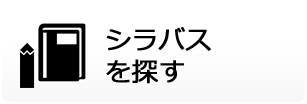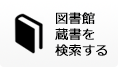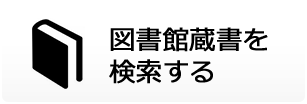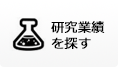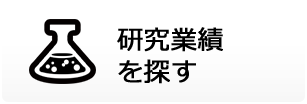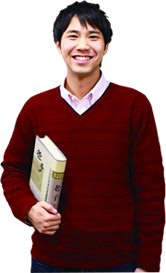2022年04月06日
「国士舘アスリートプログラム」をオンラインで実施しました
3月18日、国士舘スポーツプロモーションセンターが主催し、本学スポーツ競技会指定クラブの部員を対象とした「令和3年度 国士舘アスリートプログラム」がオンラインで実施され、本学34のスポーツ協議会指定クラブから、各部員代表ら約90人が参加しました。
今回は当センターが実施しているWG(ワーキンググループ)から「競技力向上」「安全・安心」「スポーツ倫理」の3つのテーマを取り上げ、それぞれの担当講師が登壇しました。
まず、当センター・スポーツアドミニストレーターで本学体育学部の熊川大介教授が「競技力向上のための科学サポートについて ―北京五輪に向けたスピードスケート科学サポートの事例」と題した講義を行いました。本学で行っているフィットネスチェックの詳細とアスリートの競技力を高める効果や、本年2月に北京冬季五輪に出場したスピードスケート日本代表選手団の科学スタッフとしての経験を踏まえながら、北京五輪の女子パシュート決勝などの映像とともにアスリートへの科学サポートについてレクチャーしました。
続いて、当センター・スポーツアドミニストレーターで本学防災・救急救助総合研究所の曽根悦子講師が「安全・安心WGの取り組みについて」とし、キャンパス内AED設置場所の確認、事故など緊急時の胸骨圧迫法やAED使用の重要性について説明しました。また当センター・スポーツアドミニストレーターで本学体育学部の増本達哉准教授が、本学多摩キャンパスのスポーツパフォーマンスセンターで行っているS&C(ストレングス&コンディショニング) サポートや、怪我をした場合のリハビリとしてのAT(アスレティックトレーナー)によるサポートの内容などを伝え、学内アスリートらへ活用を呼びかけました。
最後に、日本体育大学教授の関根正美氏を迎えた講義「スポーツの倫理-なぜ大学でスポーツに打ち込むのか-」が行われ、競技を行う上でのフェアプレーの考え方、世界的に行われているドーピング対策とその課題などを、実際の事例を提示しながら解説しました。また、ローマ五輪のボート競技で金メダルに輝き、のちにスポーツ哲学者として知られることとなったドイツのハンス・レンク元選手のエピソードを取り上げながら、学問とスポーツの両立や非形式的フェアプレーの実践が、スポーツ界の質の向上につながると説きました。
学生らはオンラインながら熱心に聴講し、各テーマについて理解を深める様子が見られました。
本プログラムは、クラブ横断型でスポーツやクラブ活動に関わる内容を提供することで、学生アスリートを育成する試みとして昨年度からスタートし、今回で第2回を数えました。
 熊川准教授による講義の様子
熊川准教授による講義の様子 曽根講師による講義の様子
曽根講師による講義の様子