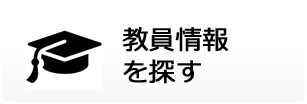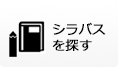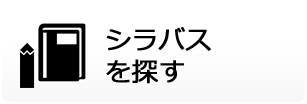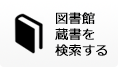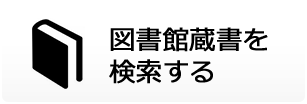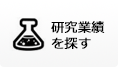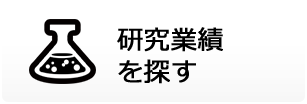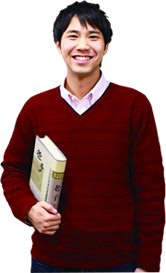2023年02月24日
「東京マラソン2023」で本学沿道救護チームが205人体制で大会運営をサポート
国士舘大学は、2023年3月5日(日)に開催される「東京マラソン2023(主催:一般財団法人東京マラソン財団)」において「沿道救護チーム」(モバイル隊・BLS隊)の派遣を行い、大会運営をサポートします。
この活動は2007年の第1回大会から毎年行っており、救急救命士を養成する体育学部スポーツ医科学科の学生、救急救命士の資格を有する同学科および大学院の卒業生、教職員など総勢205人が参加し、大会の救急体制をサポートします。
活動の主旨、目的
国士舘大学は、世のため人のために尽くせる人材「国士」の養成を目指し、「活学」を講ずる道場として1917年(大正6年)に創立しました。社会貢献すなわち、「他への献身」「真心をもって人に尽くすこと」という考え方に基づく活動の一つとして、東京マラソンにおいてボランティア活動を行っています。
沿道救護チーム(モバイル隊・BLS隊)の紹介
沿道救護チームは、主に国士舘大学体育学部スポーツ医科学科の学生、同学科および大学院の卒業生、教職員らで編成されています。
チームは、AEDを装備した救急救命士が自転車でコースを巡回する「モバイル隊」と、AEDを持ち自らの足で定点待機しランナーが倒れた場合には走って現場に向かう学生による「BLS隊」で構成しています。モバイル隊の役割 は「応急処置」と「トリアージ(傷病の重傷度・緊急度を判断すること)」です。GPSで常にモバイル隊全隊のポジションを把握することにより、患者発生の連絡から出動までの時間を短縮することが可能となり、さらに定点配置しているBLS隊と連携することにより、綿密で安全な体制を構築して大会をサポートしています。
これまでに発生した心肺停止11件では、いずれも蘇生に成功し全員が社会復帰を果たしています。
当日の沿道救護体制
救護指示センター内に設置されている「モバイル・BLS隊統括」に本学教員10人(医師および救急救命士)が配置されます。救護専用位置情報アプリを使用してモバイル隊・BLS隊とリアルタイムに連携を取りながら救護活動を統括します。傷病者の情報を把握し、救急車要請等の対応の判断や安全な搬送を行うための指示・助言を行うことにより、メディカルコントロール(医療の質の担保)を行います。
【救護チーム構成】
沿道救護本部:10人 モバイル隊:24隊48人 BLS隊:40隊80人 救護所ボランティア:67人
【人員構成】
医師:2人 救急救命士・看護師:56人 学生:147人 計205人
Zoomを用いて音声と映像で現場を把握

本大会では、本学と東京マラソン財団、中国のファーストレスポンド社が共同開発した救護専用位置情報システムにより救護本部から隊員の位置情報を把握できるほか、Zoomの音声通話とカメラ機能を活用して、現場映像を本部で確認しながら的確な指示が出せる環境を整えています。
この方法は昨秋複数のイベント救護で試験運用しており、東京マラソンの規模では初の試みとなります。今後は実証実験の成果を報告し、他のイベント救護での活用・普及を視野に研究を進めています。
喜熨斗智也体育学部准教授(専門=救急医学)コメント
ランナーが心肺停止に陥った場合、救命率は1分間に7〜10%低下していきます。まさに1分1秒を争います。倒れたランナーの元に救護チームがいち早く駆けつけるため、様々なICTを駆使して、効果的なデジタルトランスフォーメーションの取り組みに挑戦しています。
東京マラソンは世界一安全なマラソン大会を目指し、様々な団体が協力しあい、毎年救護体制の改善に取り組み、その結果、救命率100%を達成しています。
その他活動実績
本学は、東京マラソン以外にも年間約80件のイベント救護を行っています。イベント救護は、市民マラソン、トレイルラン、少年サッカー、ウォーキング、フェスティバル等の救護活動の総称です。より質の高い救護を実践するため、モバイル救護隊、救急救命士の適正配置、医師の指示、薬物投与等、本学独自の救護体制を構築しています。
参考)
「国士舘スポーツイベント等の救護活動における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策指針」
東京マラソンEXPO 2023への出展
本学は、3月2日(木)~4日(土)に東京ビッグサイト(東京都江東区)で開催される直前イベント「東京マラソンEXPO 2023」で協力団体としてブースを出展します。ブースでは、救急救命士を目指す学生による、リトルアンQCPRを用いた心肺蘇生の体験会をおこなうほか、救護チームの活動グッズやポスターを展示し、本学の沿道救護チームの活動を紹介します。
 昨年出展した「バランス測定体験」の様子
昨年出展した「バランス測定体験」の様子