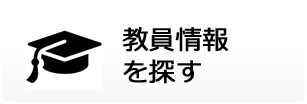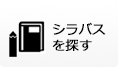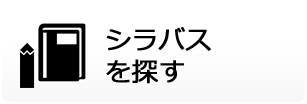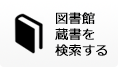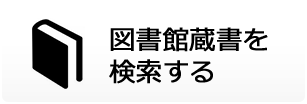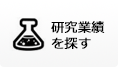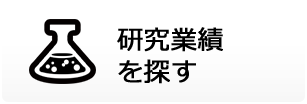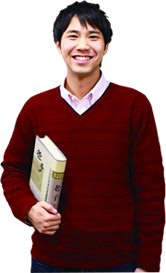2022年10月12日
世田谷区主催のSTEAM教育講座で文学部の長谷川均教授が区の地形をテーマにワークショップを開催
世田谷区が主催するSTEAM教育講座が10月8日、世田谷区立教育総合センターで開催され、文学部の長谷川均教授が集まった児童・生徒14人を対象に、ワークショップを行いました。
STEAM教育とは、文理問わず横断的な学びからIT社会に順応し、課題発見・解決能力を育む教育です。同講座は、毎週土曜日と長期休業期間を利用し、プログラミングや科学実験など学校では体験できないような学びを提供することを目的とし、今年度からスタートしました。本学を含む世田谷6大学(国士舘、駒澤、昭和女子、成城、東京都市、東京農業)と世田谷区などが連携して取り組む「世田谷プラットフォーム」が本事業に協力しており、各大学がそれぞれもつリソースを生かし、講師を派遣しています。
ワークショップでは、「地図で知る世田谷の地形」と題し、1900年代と現在の地形図を比較しながら、世田谷地域の変遷を学びました。
長谷川教授はまず、海面変動に連動した地形の形成やそれに伴う台地や平野の成り立ちを説明。世田谷地域が東京都の西側に広がる武蔵野台地に位置するなど、地形の概要や特徴についてスライドを示しながら紹介しました。その後、約100年前の世田谷地域の地図から「田」の地図記号が書かれている範囲をマーカーで塗り、田がどのような場所にあったか、景観の復元作業を行いました。そこから台地の中の川に沿って広く田が分布していたことを読み解いたほか、現在の地図と比較して、田であった場所が現在どのような土地として利用されているかを確認しました。
最後には、世田谷地域は高台に位置するものの、浅い谷やくぼ地が点在していると指摘し、これまでに水害などの自然災害に見舞われたことがあったことから、今後もし災害が発生したときにどのような行動をすればよいか、しっかり把握してほしいと呼びかけました。
参加した児童・生徒からは「昔は多くの川があったことに驚いた」「世田谷地域の土地の変化を知ることができて良かった」などの感想が聞かれ、土地の特性を理解することで災害時に適切な対策や行動につながることがわかり、自然地理学の意義を理解する機会ともなりました。
 児童・生徒らに向けて授業する長谷川教授
児童・生徒らに向けて授業する長谷川教授 ワークショップの様子
ワークショップの様子
 昔の地図から田の場所を確認する児童ら
昔の地図から田の場所を確認する児童ら 長谷川ゼミの学生も児童らをサポート
長谷川ゼミの学生も児童らをサポート
 古い地図と現在の地図を重ね合わせ、現在の地図にマーカーを塗る児童ら
古い地図と現在の地図を重ね合わせ、現在の地図にマーカーを塗る児童ら