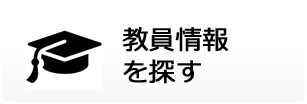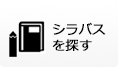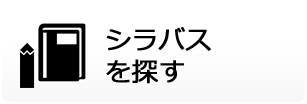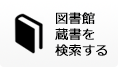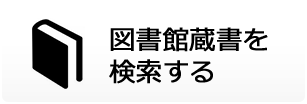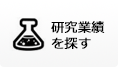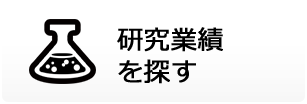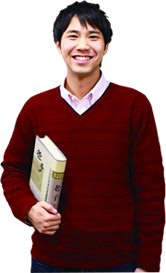2022年04月15日
【祝ご入学】令和4年度(2022年4月)新入生の皆様へ佐藤圭一学長から新入生の皆さんへのメッセージ

令和4年度入学式
式辞
国士舘大学 学長 佐藤 圭一
国士舘大学に入学された皆さん、ご入学おめでとうございます。春爛漫のこの良き日に、学部入学生3,071名、大学院入学生132名、総勢3,203名の多くの皆さんを国士舘大生として迎えますことは大変嬉しく、心よりお祝い申し上げます。また、この晴れの日のために、惜しみないご支援を捧げて来られたご家族・関係者の方々には心から感謝を申し上げます。
本日、入学された皆さんの多くは、高校3年間の内の2年間を新型コロナウイルス感染拡大への警戒という、かつて経験したことのない環境の中で高校生活を送られました。はじめて尽くしのオンライン授業、そして学園祭や部活そして修学旅行などに至るまで、中止や多くの制約を受けながらも、皆さんは学び抜かれ、卒業という大きな目的を達せられました。この4月1日からは、いよいよ最高学府での生活がスタートしました。祝福すると共に、皆さんが学生生活を送られる「大学での教育」が益々必要とされる理由について先ずはお話ししたいと思います。
2月24日ロシアによる軍事侵攻から1ヵ月半が過ぎようとしています。国際政治や世界の安全保障を巡る状況は一変しました。見るに堪えられない残酷で凄惨を極める被害が連日報道されています。無辜の人々をも無差別に、しかも集団殺害するというジェノサイドが、この21世紀に再び起きている現実を我われは知るところとなりました。戦禍を逃れてウクライナから国外に脱出した難民は420万人を超えています。
その中で、3月下旬に報じられた隣国ポーランドでウクライナ難民の支援活動を行っている方のインタビュー記事が強烈に私の心を揺さ振りました。第二次世界大戦後、東欧諸国は旧ソビエトの支配下に置かれ、「“ソ連がすべて正しい”という歴史観を押し付けられた。戦うことをしない代償として、ポーランド国民は心まで支配されてしまった」と述べた後で、「自由の中で育った人は、いとも簡単に、戦いを止めて『平和の実現を!』ということを口にします。しかし戦いさえしなければ良いのでしょうか? 言いたいことも言えない暮らしが、平和といえますか?」と逆に日本人記者に問い返したのでした。難民を助けるのは単なる親切ではなかったのです。かつてのポーランド、そして今のウクライナの人々にとって強権軍事国家の支配下での“平和は自由の死であり、民族の消滅であり、魂を奪われることであった”と記事は結んでいたのです。
“人命こそが最優先されるべきであり、自由や人権などが犠牲になったとしても平和が得られるべきであり、戦争は如何なる場合であっても絶対悪である”ことに疑問を差し挟むことなく、慣れ親しんで来た私達日本人にとっては、”命を賭してでも守ろうとする自由“とは一体何なのか? 多くの日本人の思考の枠を超えてしまうのです。
実は、その問いに答えを見出すことこそが「大学での学び」なのです。大学教育の醍醐味は、自らが志望した専門科目の修得と共に、大学生には必須の「教養」を身に付ける時間と機会が与えられています。では「教養」とは何かと云えば、「他人から押し付けられることなく、進んで様々な異なった価値観に触れ、物事の本質を理解すること。つまり、それまでの自分の思考の枠を超えて、広げて行くことのできる能力」のことであり、教養人とは、他者の気持ちに寄り添える能力と度量、そして寛容性を持った人のことを意味します。
今、世界は新型コロナウイルスによるパンデミックや、地球環境の変化に伴う異常気象、そしてこの度のロシアによるウクライナへの軍事進攻にあるように、未曾有の被害、あるいは予測不可能な状況が頻発しています。教養を身に付けた人は、冷静に物事の原因を探り判断し、目の前の事象に振り回される事の無い人、つまり、しっかりとした軸足を持っている人をいいます。また教養ある人は、道理の下、物事の核心を見抜き、譬え、体験しなくても自分とは異なる価値観を理解し、他者の心に寄り添うことができるのです。
では一体、大学人として求められる教養、混沌とした世情だからこそ求められる教養豊かな人間になるには、大学生として何をすべきでしょうか? 実はその答えは、大正6(1917)年に創立され、今年11月に105年を迎える国士舘。皆さんが入学を果たしたこの国士舘の“教育指針”と“教育理念”、そして“建学の精神”に確固たるものとして謳われているのです。 国士舘の“教育指針”は「読書」「体験」「反省」「思索」です。それらを日々励行することによって、“教育理念”である四徳目すなわち「誠意・勤労・見識・気魄」が涵養され、それらを体現することによって、本学の“建学の精神”つまり教育の目的である「国を思い、世のため、人のために尽くせる人間」すなわち“国士”となれるのです。国士舘大学は“国の将来を担う国士”を社会に送り出すことによって大学としての責任を果たし、国民の負託に応えることを使命とする大学です。
ここでは、教養を身に付けるための国士舘大学の“教育指針”について述べます。「読書」とは、学生の本分である読書すなわち書物に学び、世の中や自然界の真理を理解することです。「体験」とは、読書によって開発された知恵を持って善悪を判断して、善なる判断の下、積極的に行動することです。「反省」とは、読書により学び、体験として実行したことを、虚心坦懐に省みることです。 そして「思索」とは、「読書・体験・反省」によって導き出された自分の行為を立ち止まって精査し、新たな目標を立てることです。
国士舘大学での学生時代を、この教育指針を繰り返すことにより、「誠意・勤労・見識・気魄」が涵養され、他者の気持ちに寄り添える能力と度量、そして寛容性を持つと共に、しっかりとした軸足を持っている教養人すなわち真の“国士”になることができるのです。
そこで、皆さんにお願いがあります。世は正にスマホ時代です。電車の中でも、食事中でも、多くの若者は寸暇を惜しんでスマホを操作しています。スマホの驚異的な利便性は誰もが認めるところです。しかしながら、スマホによって失うものが、特に学生には、多過ぎると思えてなりません。非言語的コミュニケーションの媒体となっているスマホは、時として友人との語らいの機会、そして異なった考えを持つ仲間を説得し、融和や妥協点を見つける機会をも削いでいるのではないでしょうか? また自分のお気に入りの情報を集める絶好の媒体であるスマホは、限られた空間に自分を閉じ込めるため、無意識のままに偏った思想、刺激的思想にも染まってしまうことになりかねません。
それらは「教養」の育みとは真逆の関係にあります。どうか、一日の内に、スマホから離れる時間も作ってみて下さい。おっくうでも、様々な知識と情報の宝庫である新聞を広げてみて下さい。本のページを捲ってみてください。何気なく目に入る情報や、本に書かれた一節に思いがけない発見があるかもしれません。健全な国家とは、自分と異なった多種多様な人々や考え方から成り立ち、しかもそれによって人類は健康で豊かな生活を送ることができることを、どうか実感してみて下さい。大学生活は“世の中の多様性と多面性を知る絶好の機会”でもあるのです。
「人間とは他者を通して自分自身と向き合い、その接点で自己を認識する存在」です。また、大学とは真理追求の場であることからも教職員、そして仲間達との語り合い、励まし合い、喜怒哀楽を共にし、切磋琢磨し合うことが、教養を一層深め、大学を、大学たらしめている所以でもあることを理解してください。語り合える機会を積極的作ってください。言葉によって心を通じ合える友情を育んでください。大学は皆さんを応援し続けます。
最後に、今日入学式にご参集頂いたご家族、保護者の皆様にもお願いがあります。国士舘大学の4年間で、授業や課題に必死で取り組むことにより、お子様達は心身ともに、見違える程大きく成長します。しかしながら、全学的な指導体制を整えているとはいえ、途中離脱する学生も出てしまうことも事実です。折角、選んで頂いた国士舘大学です。彼らの夢実現のために、我々教職員と共に、緊密に連絡を取り合い、最後まで協力体制を整えて行きたいと思います。どうか、ご協力を賜りたく存じます。
4年後あるいは2年後の3月20日、皆が満面の笑みで、互いの友情と健闘を称え合う「卒業の日」、その日を心から盛大にお祝いすることが、私たち国士舘大学・教職員一同の最大の願いです。大学生活がスタートしました。皆で、実り多く、悔いのない学生生活を送りましょう! 入学生の皆さんの前途を祝福致します。入学おめでとうございます!
令和4年4月8日