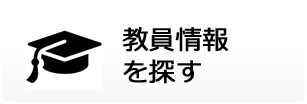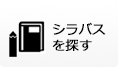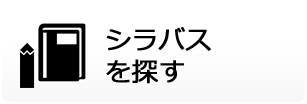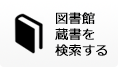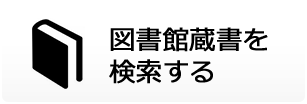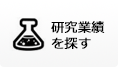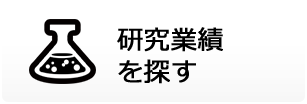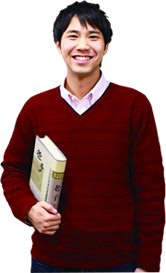2021年10月25日
東京2020大会で本学園関係者がボランティアなどで活躍しました
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会(以下、東京2020大会)が57年ぶりに東京で開催され、本学からは在学生・卒業生合わせて7人が選手として参加したほか、本学園関係者約340人がボランティアや競技スタッフ、医療サポーターなどさまざまな役割を担い活躍しました。
東京2020大会終了後、在学生を対象に実施したボランティア活動アンケートでは、大会ボランティアや都市ボランティアに58人が参加したと回答しました。また、各関係機関からの支援要請を受けた学生・生徒141人が会場内外で活動しました。
医療スタッフとしては、各会場の医務室で142人の本学学生・教職員が活動したほか、体育学部スポーツ医科学科や防災・救急救助総合研究所などの教職員や救急システム科の大学院生ら18人が「会場医療責任者(MOM)」として、同学科の学生118人がMOMサポーターとして首都圏の約30会場に派遣されました。また、大会医療体制の中枢である医療調整本部を本学教職員の医師や救急救命士ら6人が担い、病院搬送時の医療機関への連絡、調整や各会場のMOM・MOMサポーターとの調整などを行いました。
 選手村でボランティア活動を行った学生
選手村でボランティア活動を行った学生 自転車競技ロードレースのコースサポーターを務めた学生
自転車競技ロードレースのコースサポーターを務めた学生
 医療チームとともに競技前の搬送法を確認
医療チームとともに競技前の搬送法を確認 MOMサポーターとして会場を見つめる様子
MOMサポーターとして会場を見つめる様子
ボランティア体験記
井上陽帆さん(文学部4年)
 選手村で偶然会った文学部の江川陽介教授(右)と。江川教授はフィリピン選手団柔道チーム専属トレーナーとして選手村に滞在していた
選手村で偶然会った文学部の江川陽介教授(右)と。江川教授はフィリピン選手団柔道チーム専属トレーナーとして選手村に滞在していたきっかけは、教授から配付されたシティキャストの応募用紙でした。一生に一度あるかないかの経験ができるとの思いから応募し、さらに自らフィールドキャストにも応募しました。
新型コロナウイルスの影響で結果的にはフィールドキャストのみの参加となりましたが、オリンピック・パラリンピックで活動した23日間は、活動前に抱いていた期待をはるかに超える日々でした。
私は、選手村のメインダイニングホールという、大会の選手や関係者だけが利用する食堂で活動していました。利用者のカードの確認や歩行ルートの誘導、机上や椅子の整頓、感染対策の呼びかけなど多様な業務を行いました。
活動の中で印象に残った思い出は、外国の選手らと多くのコミュニケーションをとったことです。私は英語が得意ではないのですが、言葉が伝わった時や日本語であいさつを返してくださった時は達成感があり、やりがいにつながっていました。パラリンピックでは、視覚障害の選手のトレーを持って誘導することもあり、一層距離を近くに感じることができました。交流した際に各国選手らからいただいたピンバッヂの数々は思い出として家で大切に飾っています。
同じ思いを持って参加したボランティア同士の年齢を超えた交流もあり、一人一人との出会いが大切なものとなりました。
なにより、外国かと思うような選手村のオープンで高揚した空気を忘れることはできません。私が味わうことのできた大会の一端を、将来体育教師になった時に、生徒に伝えていきたいです。