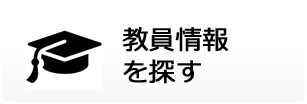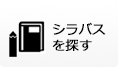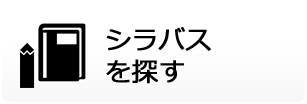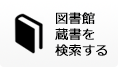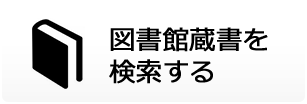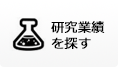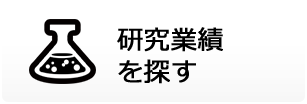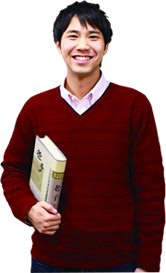2023年10月25日
アスリートにスポーツカウンセリングを【秋葉茂季体育学部准教授】
本学には、各競技に打ち込む学生アスリートが多数在籍します。今年5月に開始したスポーツカウンセリング事業で相談員を務める秋葉茂季体育学部准教授(スポーツ心理学)に、本事業について、そして勝敗の世界で生きるアスリートの心理についてうかがいました。
 秋葉茂季准教授
秋葉茂季准教授
スポーツ心理学を専門とされたきっかけは
私が国士舘高校3年生の時に、硬式野球部のキャプテンとして甲子園に出場したのですが、私のエラーで負けてしまいました。非常に苦い経験でしたが、その頃から「一生懸命頑張っている競技が自分にとってどんな意味があるのか」を考えるようになりました。そして、本学文学部での学びを通して、その考えは「どのような体験が人格形成に寄与するのか」と具体的になり、3年生から教育心理学と本格的に向き合いました。その後も少しずつテーマは変わっていきましたが、根本には「スポーツが人格形成にどう寄与するのか」というテーマはずっとありました。そして、学びを深めるうちに臨床心理学にたどり着き、日本スポーツ心理学会認定の「スポーツメンタルトレーニング指導士」を目指して大学卒業後は日本体育大学の大学院へと進学しました。
スポーツメンタルトレーニング指導士は、大学院修了に加えて現場研修が必要で、母校の国士舘高校硬式野球部でコーチをしながらチームの心理サポートも行い現場経験を積みました。資格取得後は、国立科学スポーツセンターでさまざまな日本代表チームの心理サポートに従事しました。その時に、心理グループのアドバイザーだった中込四郎本学特任教授(当時)とのご縁で平成27年に本学教員として入職しました。
本学で5月からスタートしたスポーツカウンセリング事業は、以前から機能としてはあったのですか

以前から中込教授と私で希望者がいればスポーツカウンセリングをしていました。その機能が5月からスポーツカウンセリング事業として結実したのです。ここには、当時から指導者や選手から「どうやったらよりうまくいくのか」というポジティブな相談が多く寄せられていました。本学の指導者は元日本代表選手も多く、我々の活動に理解があります。カウンセリングをどう活用するかも学んできているので、やりとりが明確です。我々が現場に出向いて指導することもあり、指導者と連携して現場の心理的問題を解決するなどさまざまな機能を持っています。カウンセリングと聞くと「意見箱」のように広く意見を聞くところのように思われるかもしれませんが、ここは現場とつながりながら、サポートを必要としている人に手を差し伸べられるような設定をしています。
先生が専門とするスポーツカウンセリングとは
無意識のものを意識化へと橋渡しのサポートをするのが我々の仕事です。例えば、選手にカウンセリングを通して、選手が自身の特徴をよく理解して自分とつきあえるように導きます。また、選手だけではなく指導者へのカウンセリングも重要になります。指導者もまた自分自身を理解することがとても大切で、我々が介入して「本質はここにあるのでは」と示唆することによって現場が回りだすこともあります。
選手が自身と向き合うことは、その後の人生にも影響がありそうですね
「なぜこの競技に打ち込んでいるのか」「自分が競技をする意味とは」を選手である間に理解することは大事です。競技生活を終えた時、選手時代に得たものが何なのかを、その人の中で落とし込んで次の世界へ踏み出す、そのための導きや手助けも我々の仕事のひとつです。我々が携わるのは、競技力向上や実力発揮というところだけではなくて、その後のキャリアや、メンタルヘルス、人間関係のコミュニケーションもサポートの対象になっています。
 カウンセリングルームでの秋葉准教授
カウンセリングルームでの秋葉准教授 カウンセリングの際に写真のような道具を使うこともある
カウンセリングの際に写真のような道具を使うこともある
今、問題になっている学生アスリートの薬物依存についてはどのようにお考えでしょうか
基本的に大学生という年頃は、発達年代として薬物やギャンブル、アルコールなどに興味を持つ年代なので、おそらくアスリートだけではなく同じような世代の人たちに広くまん延しているのだと思います。基本的には「自分が変わりたい」だとか、「自分が何だかよく分からない」といったときに、何か方向を示してくれるような強いものに惹かれる年代ではあると思うので、「違った自分になれる」「見たことないものに触れる」という体験に興味をそそられるのではないでしょうか。
アスリートは、完璧主義なところがあります。「これ」と決めたら、それをやらないと気が済まなくなってしまう。それが競技に向くから競技力が上がっているのです。競技で発散されていたエネルギーの行き場がなくなってしまった時、近くに薬物など依存性の高いものがあると、そちらにエネルギーが一気に向いてしまうことがあります。
アスリートで薬物などに興味を持つ人たちというのは「自身が今やりたいことに全力を出せていない」「やらねばならないことがあるのに、うまくいっていない」という状態で、競技以外にエネルギーが流れてしまっているのではと思います。間違った方向に向かったエネルギーをその人が本当にやりたいこと、適切な方向に向けてあげられるような援助が必要だと思います。
そういう意味では、「なぜこの競技を一生懸命やっているのか」「どこが好きなのか」など、自分が競技に向かう意味を現役時代にしっかり理解することが、とても大切になってきます。
アスリート以外にもスポーツメンタルトレーニングは必要とされていますね
 カウンセリングルームでの秋葉准教授
カウンセリングルームでの秋葉准教授一般企業の営業職や医師、将棋の棋士など、持っているパフォーマンスをどう発揮したらいいのか、またチームビルディングやチームパフォーマンスをどう上げるのかなどの現場に呼ばれることもあります。
その際に、「どうしたら緊張がほぐれますか」という質問を受けることがあります。そんな時は「年老いていくと緊張する場面すらなくなっていくのだから、むしろ緊張を味わって、それで失敗して悔しい思いをしたら、それは向上心の証であり継続につながる一歩なので、良いことだ」とお伝えしています。
緊張は未経験に対する不安から起こるもので、裏を返せば新たな体験をしている証拠です。その体験はその人を成長させてくれます。ですので、緊張はポジティブなものなのです。自分作りをするときには、体験や経験という材料が必要です。緊張の場面を避けるということは、材料を得る機会を逸するということです。ですから、多くのチャレンジをして失敗して、己を探求することが人生を豊かにすることだと思います。
今後スポーツカウンセリング事業にもとめられるものとは
欧米では、以前からスポーツ分野でカウンセラーは身近な存在で、日本でもカウンセリング需要が年々高まっています。しかし現在、日本スポーツ心理学会認定のスポーツメンタルトレーニング指導士は決して多いとは言えません。そんな中、大学の現場で指導できる立場をいただいているので、これからのスポーツ界に必要不可欠な人材である指導士の育成に努められたらと思っています。
学生へのメッセージをお願いします
単一的な経験よりも、さまざまなことを多角的に経験するとはとても大事です。新しいことを見聞きし、普段と違うことを体験するなど、学生の今だからできることがたくさんあるはずです。すぐに結果を求めず、今は中途半端でも理解しきれなくてもよしとして欲しいです。その後の人生でそういうものが全部繋がって一つのものが出来上がればいいのですから。私は、甲子園の“悪夢”と向き合い多岐にわたる経験をすることにより、スポーツカウンセリングという道を見出せました。
 長野県の小学生にメンタルトレーニングセミナーを行う秋葉准教授
長野県の小学生にメンタルトレーニングセミナーを行う秋葉准教授