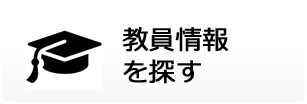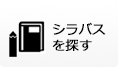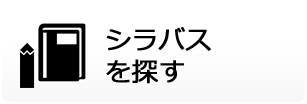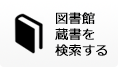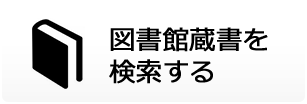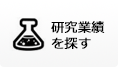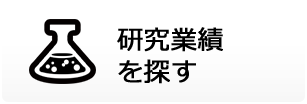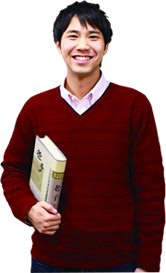2023年09月01日
世田谷区主催のSTEAM教育講座で文学部の小野瀨倫也ゼミがワークショップを開催
世田谷区が主催するSTEAM教育講座が8月26日、世田谷区立教育総合センターで開催され、文学部の小野瀨倫也教授とゼミ生6人が、集まった小学5・6年生15人を対象に、ワークショップを行いました。
STEAM教育とは、文理問わず横断的な学びからIT社会に順応し、課題発見・解決能力を育む教育です。同講座は、毎週土曜日と長期休業期間を利用し、プログラミングや科学実験など学校では体験できないような学びを提供することを目的とし、令和4年度からスタートしました。本学を含む世田谷6大学(国士舘、駒澤、昭和女子、成城、東京都市、東京農業)と世田谷区などが連携して取り組む「世田谷プラットフォーム」が本事業に協力しており、各大学がそれぞれもつリソースを生かし、講師を派遣しています。
ワークショップでは、「骨パズルを完成させよう!」と題し、ヒトの骨の形から体のどの部分の骨かを想像し、グループでパズルを完成させる体験を行いました。
自己紹介やクイズを通してアイスブレイクをした後、さまざまな骨の形が書かれた画用紙が配られました。まず、参加児童らはパーツを切ってボタンで留め、自分なりに骨パズルを組み立てた後、3~4人のグループで相談しながら完成を目指しました。途中で服を着た人体模型が登場し、児童らは服の上から各パーツを触って骨の形を確認するなどしながら、最終的に各グループで完成させたパズルが並べられました。
小野瀨ゼミの学生らは、参加児童らに寄り添いながら骨パズル作成の補助をしました。ワークショップの進行役を務めた小野瀬ゼミに所属する村松健斗さん(文3年)は、「重いものを支えられるような骨の形や、細かい動きができるように先端にいくほど骨の数が多いといった構造の特徴など、随所に骨の仕組みがわかるような説明を意識した。初対面の人とグループで話し合うのは難しいものだが、相手の意見を聞いて考え直したりする様子も見られた。小学校教員を目指しているので、将来こういった学びの機会を作っていきたい」と話しました。
参加した児童からは「肘から手にかけての腕の骨が2本あることに驚いた」「自分の腕を触ったり人体模型を触ったりすることで骨の形がわかり面白かった」などの感想が聞かれ、骨パズルを通して人体の不思議を感じる機会となりました。
 あいさつする小野瀨教授
あいさつする小野瀨教授 思い思いに骨パズルを組み立てる
思い思いに骨パズルを組み立てる
 小野瀨ゼミの学生が作業をサポート
小野瀨ゼミの学生が作業をサポート 組み立て方をグループで相談
組み立て方をグループで相談
 服の上から人体模型を触って骨の形を確認する
服の上から人体模型を触って骨の形を確認する 進行役を務めた小野瀨ゼミの村松さん
進行役を務めた小野瀨ゼミの村松さん