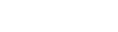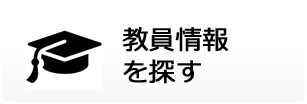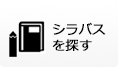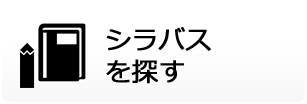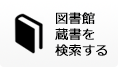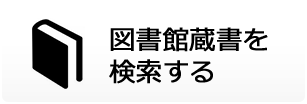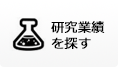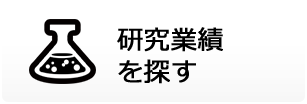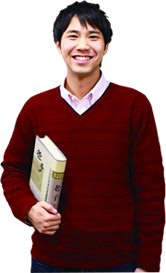2022年06月03日
世田谷区立教育総合センターで防災時避難所運営研修会を実施しました
本学地域連携・社会貢献推進センターは5月27日、世田谷区教育委員会事務局との協働による防災時避難所運営研修会を世田谷区立教育総合センターで実施し、本学防災・救急救助総合研究所の浅倉大地助教と中林啓修准教授を講師に、世田谷区職員ら18人が参加しました。
はじめに、地域連携・社会貢献推進センターの村上純一センター長があいさつし「地域連携の強化を目的に、さまざまな取り組みを具現化する計画の第一歩として研修会が開催され喜ばしい限り」と述べ、本研修会の開催の意義と成果に期待を寄せました。
つづいて、浅倉助教が避難所に関する基礎的な知識について説明し、参加者は避難場所の種類や避難所の役割、避難所運営のマニュアルフローについて確認しました。
その後、2グループに分かれHUG(避難所運営ゲーム)を行いました。HUGでは、会場を避難所と仮定し、参加者は避難所を運営していく立場として、避難所運営準備から避難者の振り分け、トラブル対応などを約60分間模擬体験をした後、互いのグループの対応を比較しながら工夫した点や課題などを共有し合いました。
ゲーム終了後、中林准教授は「避難所運営に正解はない。空間の使い方を理解し、必要なことは何かを考えることが大切」、浅倉助教は「訓練を繰り返し行うことで、どんな備蓄品が必要か、導線の管理はどうするのかなどブラッシュアップしていけると思う。研修を継続的に行い、実際の備蓄や導線をイメージしながら計画をしていってほしい」とそれぞれ参加者にアドバイスを送りました。
研修会の最後には、世田谷区教育委員会事務局教育政策部乳幼児教育・保育支援課長の本田博昭氏から「今回、実際のリアルな訓練をしたことでいろいろ考える良い機会になった。本施設が避難所に指定されたら、協会や自治体と協議しながら、避難所運営について深く考えていきたい」とあいさつがあり、約2時間の研修会を締めくくりました。
研修後、参加者からは「世田谷区立教育総合センターを避難所として疑似体験をすることで、何が危険で、何に配慮すべきか学ぶことができた。実際に直面した場合、難しさもあるが予備知識を得ることにより、今後の展開につなげていきたいと思う」と感想が述べられました。
本学は、多様な学問分野における成果を地域・社会により広く還元するための機能強化を図るため、令和4年度より「生涯学習センター」を改編・名称を変更して、「地域連携・社会貢献推進センター」として新たにスタートしました。
 あいさつする村上センター長
あいさつする村上センター長
 浅倉助教
浅倉助教
 説明を受ける参加者ら
説明を受ける参加者ら HUG(避難所運営ゲーム)の様子
HUG(避難所運営ゲーム)の様子

 トラブル対応をホワイトボードに記入
トラブル対応をホワイトボードに記入
 会場の様子
会場の様子 本田氏
本田氏