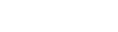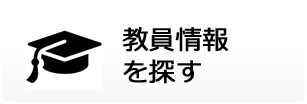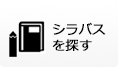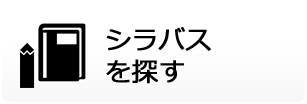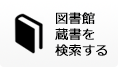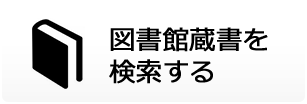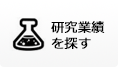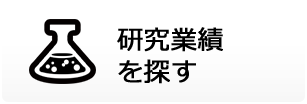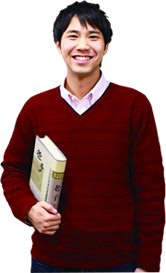2022年09月10日
「防災リーダー養成論実習」を世田谷および多摩南野キャンパスで実施しました
世田谷キャンパスで8月22日から9月2日、多摩南野キャンパスで9月5日から10日にかけて「防災リーダー養成論実習」を実施しました。
この授業は、災害対応のための知識と技術を習得する実践的な集中実習として毎年実施されています。今年は7学部から464人の学生が参加し、8チームに分かれて実習が行われました。
防災知識を幅広く体系的に学び、発災時には地域で災害対応のリーダーとして貢献できる人材を養成するための本講義および実習は、防災・救急救助総合研究所がカリキュラムを構成し、運営を行う本学独自のプログラムです。毎年、時勢やニーズに即した要素を取り入れて改良を重ねることにより、現場で実際に動くことを前提とした実践的な内容となっています。
座学実習では、過去の震災実例をもとにした防災の基礎知識をはじめ、近年大きな被害をもたらす水害について学ぶ「日本の河川災害と対策」、各自が自分の居住地域の防災対策を見直して避難計画を立てる「マイ・タイムライン」、災害時にボランティアセンターを立ち上げるシミュレーション実習やHUG(避難所運営ゲーム)、あらゆる被災者のニーズを予測するワークショップなどを行いました。また体育館などの広いフロアで実際に身体を使って学ぶ応急手当、搬送法、初期消火、ロープワークや、マネキンを使用したBLS(一次救命処置)、避難所の間仕切り設置など、実践をともなう訓練も幅広く実施しました。
災害時における要支援者への対応についての実習では、受講学生らは聴覚・視覚に障がいがある被災者の案内・誘導や、車いす介助の実践を行いました。また「被災者の心理把握とコミュニケーション技能」では、よりきめ細やかな被災者対応に結びつく傾聴やストレッチの効能なども身につけました。ボランティアセンター立ち上げ訓練では、世田谷キャンパスではせたがや災害ボランティアセンター、多摩南野キャンパスでは多摩市社会福祉協議会の職員を招いてボランティア募集や統括についての講義も行われました。こうした幅広く多角的なプログラムを体験することで、受講学生は災害時に果たすべき役割をより深く自覚する機会としていました。
配布された非常食や簡易トイレを各自が自宅で使用し、実習期間中の自分の水分摂取量を測定するなど帰宅後にも実習に取り組んだ学生らは、3日間の対面実習終了時には、それぞれが防災リーダーへの第一歩を踏み出す意識を新たにしていました。
世田谷キャンパス(8月22日~9月2日)
 災害時救護の基本対応についての講義
災害時救護の基本対応についての講義 東日本大震災の事例で避難について学ぶ
東日本大震災の事例で避難について学ぶ
 視覚障害の被災者対応実践
視覚障害の被災者対応実践 初期消火訓練
初期消火訓練
 車いす介助の実践
車いす介助の実践 被災者心理とコミュニケーションについての講義
被災者心理とコミュニケーションについての講義
 避難所運営シミュレーションをチームで学ぶ
避難所運営シミュレーションをチームで学ぶ せたがや災害ボランティアセンター職員による講義
せたがや災害ボランティアセンター職員による講義
多摩南野キャンパス(9月5~10日)
 BLS(一次救命処置)を学ぶ学生ら
BLS(一次救命処置)を学ぶ学生ら 被災者のニーズを予測するワークショップ
被災者のニーズを予測するワークショップ
 避難所でのプライバシーを確保する間仕切りの組み立て訓練の様子
避難所でのプライバシーを確保する間仕切りの組み立て訓練の様子 災害を想定した避難所開設・運営訓練を実施し、動線を考える学生ら
災害を想定した避難所開設・運営訓練を実施し、動線を考える学生ら
 さまざまな事情を抱えた避難者への対応も体験
さまざまな事情を抱えた避難者への対応も体験