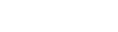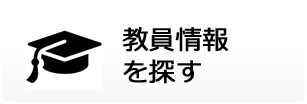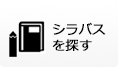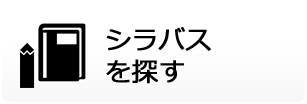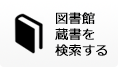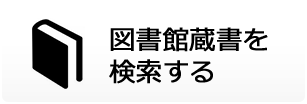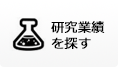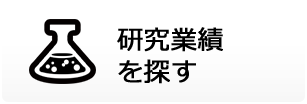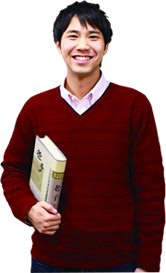2022年06月28日
セネガルで開催のSDGsプロジェクトで本学学生・教職員らが各国参加者らと意見交換しました
ヨーロッパ非政府スポーツ機構青少年部門(European Non-Governmental Sports Organization Youth=ENGSOユース)によるアフリカ、アジア、欧州におけるスポーツ指導者育成研修プロジェクトの一環として、「セネガル青年交流会」が5月9日から同14日まで、セネガル共和国の首都・ダカールで開催され、本学のほかハンガリー、セネガル、フランスの5団体・40人が参加しました。交流会は、スポーツを通じてSDGsに貢献することを体験的に学び、文化の異なる海外の青年と交流することを目的とし、セネガル・オリンピック委員会が主管しました。約10カ国以上の国籍の参加者が集う中、それぞれの言語・文化をもつ若者たちが、ワークショップや競技施設の視察などを通して多様な事例に触れながら、スポーツにおける持続可能な社会の実現について考えました。
日本から参加したのは、体育学部の田原淳子教授を団長に、体育学部こどもスポーツ教育学科3年の坂本絵子さん、同体育学科3年の黒澤楓菜さん、法学部法律学科3年の田代怜愛さん、文学部史学地理学科4年の坂本渉さん、21世紀アジア学部4年の髙崎大樹さん、防災・救急救助総合研究所の曽根悦子講師、国士舘スポーツプロモーションセンター職員の大平卓真さんの8人。期間中は、各国の文化紹介を通した交流も活発に行われ、学生らは参加者らとともに箸や扇子のほか折り紙を教えて皆で紙飛行機を飛ばしたり、紙相撲でトーナメントを実施したり、日本のお菓子をふるまったりするなどして日本の文化を紹介し、交流を深めました。
参加した学生からは、「スポーツがSDGsの目標達成に大切な役割をもつことがわかった」「一人一人の取り組みの積み重ねの大切さを実感した」「理念や活動を世界中に広げるにはオリンピックは大きな機会となる」など持続可能な社会の実現に向けた個々の役割を実感する感想が寄せられたほか、「他国の参加者の思考力・判断力・表現力を目の当たりにし、自ら考えて疑問点を見出し周囲と共有する姿が印象的だった」「グループワークで質問や意見がなかなか思い浮かばず、悔しさが残った」「性別を問わない意欲的な社会参加が必要だと感じた」といった感想も。海外渡航が初めてという学生が多数を占め、参加にあたっては3回の事前研修をはじめ、略歴書や参加動機などの英文による文書作成、現地病に備えてのワクチン接種など、入念な準備についても学ぶ機会となりました。
田原教授は今回の交流を「学生たちがさまざまな背景をもつ国々の人たちの多様な考えや主体的に行動する姿に刺激を受けて知見を広め、共通の事例をもとにSDGsを発展的に考えることができた」と評価し、「学生たちは今後、スポーツにおけるSDGsの発信者、推進者としての役割を担うことができるのでは」と期待を寄せました。
本プロジェクトは、持続可能社会の創造を目標に若年者に対するスポーツと教育に関するプラットフォーム構築などを図る目的で2020年にスタートし、本学はアジアで唯一の参加団体として、オンライントレーニングマニュアルの作成や青年スポーツコーチの育成、途上国のスポーツ機会の創出、スポーツ環境の整備などに取り組むこととしています。これまでは、コロナ禍によりオンラインでのセミナーや意見交換を実施してきました。今年9月にはスポーツ指導者を対象に、本学が幹事校となり日本での開催を予定しています。
 グループワークで「スポーツにおけるSDGs」を議論する様子
グループワークで「スポーツにおけるSDGs」を議論する様子

 現地の食事を楽しむ参加者ら
現地の食事を楽しむ参加者ら
 参加した学生と教職員ら
参加した学生と教職員ら 本プロジェクトのユニフォームを着て集合写真
本プロジェクトのユニフォームを着て集合写真
 児童福祉施設で関係者から話を聞く参加者
児童福祉施設で関係者から話を聞く参加者 現地のサッカークラブを視察
現地のサッカークラブを視察
 自由時間に交流する様子
自由時間に交流する様子 折り紙など自国の文化を紹介し交流を深める
折り紙など自国の文化を紹介し交流を深める
 バラ色の湖「ラックローズ」を観光する参加者
バラ色の湖「ラックローズ」を観光する参加者 ラクダ乗りツアーを体験
ラクダ乗りツアーを体験