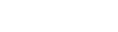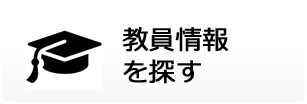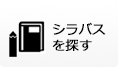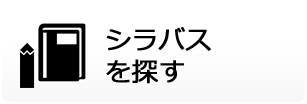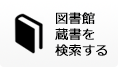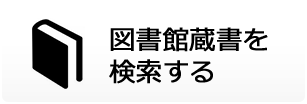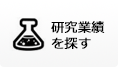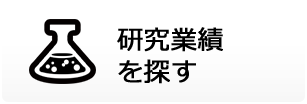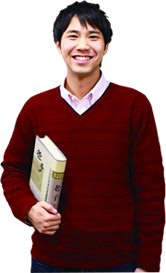2019年03月26日
第9回防災シンポジウムを実施しました
本学防災・救急救助総合研究所(防災総研)は3月23日、世田谷キャンパスのメイプルセンチュリーホール1階大教室で「第9回防災シンポジウム」を開催しました。今回のテーマは「地域の防災力を高めるには」ということもあり、会場には地域住民ら約90人が来場。兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科の室﨑益輝教授による基調講演や学生・職員による発表、パネルディスカッションが行われました。
室崎教授は基調講演で、近年の自然災害で死者数が増加していることを紹介し、原因を「自然の凶暴化と社会の脆弱化」としました。社会の脆弱化とは、「町内会や自治会などの地域コミュニティの不活発」と説明し、実際の例として、発災時に自治会などが協力して集団避難した地域と、個人避難をした地域では、被害に大きな差が出たことを紹介しました。
続けてコミュニティの大切さを説き「コミュニティによって生まれる自衛性、自律性、連帯性が被害縮小につながり、復興も早い」と述べ、地域コミュニティと地域防災が密接な関係にあると述べました。最後に「地域防災は、日ごろの連携から発揮されるので、地域にどんな人がいるのかを互いに把握し合い、交流を深めてほしい」とまとめました。
学生・職員の発表では、「災害ボランティアに参加した経験」や「東日本大震災を被災して感じたこと」などが述べられました。
まず、発表を担当した防災総研の浅倉大地職員は、職員目線で経験した災害ボランティアについて語りました。浅倉職員は、これまで学生を引率して被災地でボランティア活動を行った経験から、「被災地で皆が真剣に考え悩んでいるところに、学生が一員として入り込むことは、学生にとって貴重な経験となる」、「発災時に現場を知っている学生が近くにいれば力になる、よって地域防災力向上につながる」と述べ、学生が災害ボランティアを経験することは、学生と被災地の双方にとって価値があるとまとめました。
次に発表した体育学部4年の千賀嘉子さんは、宮城県南三陸町出身で東日本大震災に被災した経験と、本学の災害ボランティアに参加した経験を語りました。被災者とボランティアという双方を経験から「被災地の復興に役立つのは若い力」とし、被災地の経験を学生に伝えていくことが大切だと述べました。
最後に発表したのは政経学部1年の徳元菜摘さん。徳元さんは、本学の防災教育科目「防災リーダー養成論」「防災リーダー養成論実習」を受講したことを話し、「防災意識を高めるきっかけになった」と語りました。続けて「防災について興味を持つことで、自分や周りの人を助けられるかもしれないし、発災時は正しい選択ができるのではないか」と述べました。また、「学部で勉強している行政の分野からも防災を意識していきたい」と意欲を見せました。
パネルディスカッションでは、パネリストに室﨑教授、アウトドア防災ガイドのあんどうりす氏、世田谷区危機管理室の工藤誠室長、世田谷区若林町会広報担当の月村雅一氏、本学防災総研の月ヶ瀬恭子講師の5人を迎え、元NHK解説委員で防災総研の山﨑登教授がコーディネーターを務めて進行しました。
ディスカッションでは、本シンポジウムのテーマ「地域の防災力を高めるには」を中心に、防災対策や避難経路、大学や行政の取り組みなどについて意見が交換されました。
パネリストからは、各市区町村で防災意識の度合いが異なる中で「民間企業も巻き込んで防災力を高めたい」「さまざまな場所に出向いて、各地域の防災意識を促していく」などの提言がありました。
 基調講演を務めた室﨑教授
基調講演を務めた室﨑教授 パネリストを務めた、あんどう氏
パネリストを務めた、あんどう氏
 月村氏
月村氏 工藤室長
工藤室長
 月ヶ瀬講師
月ヶ瀬講師 室﨑教授(左)とコーディネーターを務めた山﨑教授
室﨑教授(左)とコーディネーターを務めた山﨑教授
 パネルディスカッションの様子
パネルディスカッションの様子